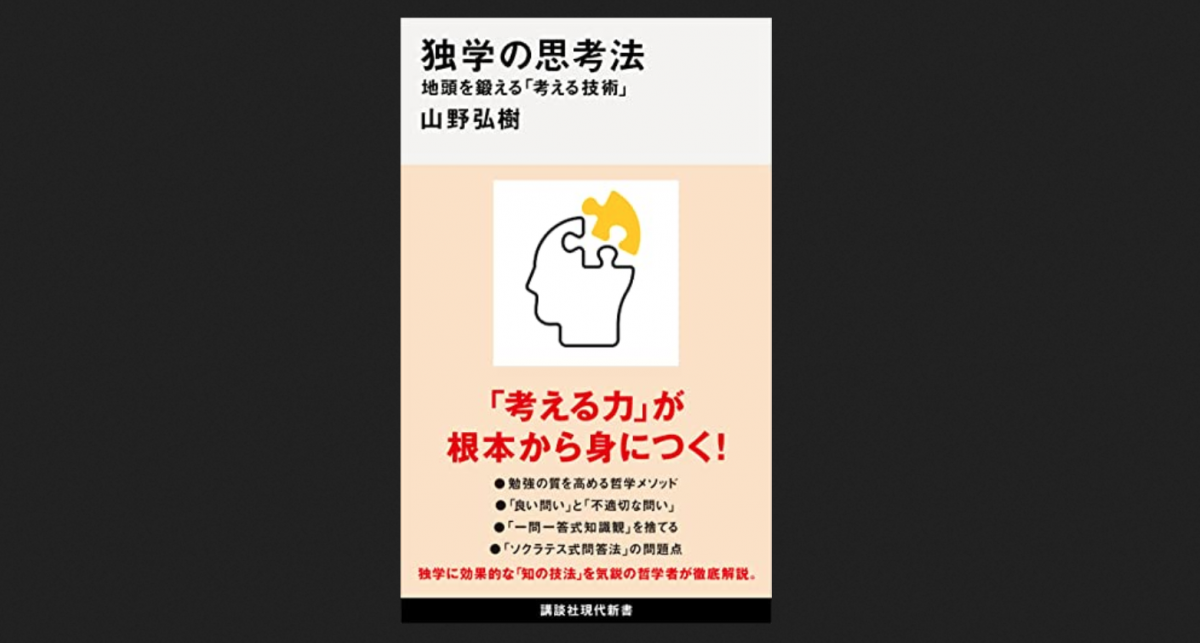副題が”地頭を鍛える「考える技術」”とあり、タイトルを含めてキャッチーなキーワードが詰め込まれているが、一旦それらを外して冷静に本書に向き合ってみよう。
まず、「独学の思考法」とあるが、独学する上でどんな本を選び、どう本を読めばいいのかといった具体的なノウハウが提示されているわけでもないし、いかなる勉強スタイルが効果的なのかという説明があるわけでもない。むしろ、より汎用的な「思考の技術」が語られている本である。
まず本書では、不確実な時代・確実な答えがない時代では、「いかにして自ら思考する力を身につけられるのか」が喫緊の課題になっていると説く。その上で、著者は独学を二つに分類する。「達成のための独学」と「探求のための独学」だ。
まず「達成のための独学」は、いわゆる試験勉強をイメージすればいい。ある枠組みの中で答え(正解)が決まっており、いかに短時間で効率的にその答えにたどりつけるのかを競うための学習だ。
一方「探求のための独学」は、そうした「すぐに答えが出る」のではない問いと向き合うプロセスを指す。本書が提示するのは、そのような独学における「考える技術」である。その意味で、独学の思考法というよりは、独学に役立つ(あるいはその基礎となる)思考法、というのがイメージに近いだろうか。
二つの思考アプローチ
では、その思考法とはどのようなものだろうか。
第一部「原理編」では、問いを立てる力・分節する力・要約する力・論証する力・物語化する力が列挙されている。これは、『知的生産の技術』の著者梅棹忠夫による知的生産の定義「知的生産というのは、頭をはたらかせて、なにかあたらしいことがら──情報──を、ひとにわかるかたちで提出することなのだ」に呼応すると考えられる。きわめて基礎的な能力だ。
また、そうした能力をいかに使うのかの方向性の提示は1969年からほとんど動いていないと考えられる。自ら問いを立て、その問いに取り組み、最後にそれを他者へと伝えるために整理すること。私は拙著『Evernoteとアナログノートによる ハイブリッド発想術』で、そのプロセスを「着想・連想・整想」の三段階に見立てたが、どのような切り口を立てるにせよ、こうした段階的なアプローチは必須だという点は共通しているだろう。
本書が面白いのは、ここからである。第二部「応用編」では自らの頭の中で思考を発展させていくのではなく、むしろ他者との対話で思考を深めていく技法が開示される。基本的に「知的生産の技術」が、個人の(個人で完結する)技法として扱われてきた歴史を考えれば、これはなかなか異端であり、逸脱であり、新展開であろう。でもって、まさに現代で必要な技法でもある。
まず「対話」と「思考」と言われてすぐに思い浮かぶ「ソクラテス式問答法」について本書は否定的な立場をとる。非常によくわかる話だ。あれこそまさに「使用上の注意・用法を守ってご利用ください」の最たるものである(ソクラテスが最後にどうなったのかを思い浮かべると良い)。ある程度信頼関係がある中では、非常に効果的な方法ではあるのだが、コンテキストを共有していない相手や、恐怖心や欠損した自尊感情、満たされない承認欲求、イデオロギーへの盲信などに満ちあふれている人に対して行えば、まともな対話が成立する望みはきわめて小さい。それが言葉だけのインターネットの場で行われれば、さらにその可能性は小さくなる。
よって、新しい方法が必要である。本書では、「問い」を媒介として対話を成立させるアプローチが紹介されるのだが、そこで役立つのが第一部で解説された自らの問いを深める力なのだ。自らで問いを立て、その問いそのものについて考えていく(なぜ、自分はそう考えたのだろうか? など)というそのアプローチを、そのまま他者の発言にも向けるわけだ。詰問口調で攻め寄るのではなく、むしろ好奇心を持って相手の発言に寄り添っていくこと。ここで、自己へのまなざしと他者へのまなざしが重なることになる。
本書の他の部分も同様だ。第一部で確認された「自ら思考する力」がそのまま第二部で他者と対話する力へと展開されていく。この重なり合いこそが、「知的生産」の面白いところなのだ。その点は、拙著『すべてはノートからはじまる あなたの人生をひらく記録術』でも確認した。自分のためのノートは他人のための本になりうるし、他人が書いた本は自分のためのノートになりうると。そういう多重性を認識することが、もう一段深い思索のステップとなる。
スティーブン・スローマンとフィリップ・ファーンバックの『知ってるつもり』でも確認されているように、人類は認知的分業を得意とし、それによって文明・文化を発展させてきた。個が個であると共に、集合の一部にもなりえる、という多重性。井戸を掘っていけば、別の場所に抜け出るということ。私たちの脳=思考は、閉じているように思えて、たくさんの小さな穴が空いているのである。そこからいろいろなものが出入りしている。そのことに目をつぶるのは、あまり健康なことではない。
自らで思考を深め、他者と共にそれを広げていくこと。その両方が、「思考」にとって必要なのだ。少なくとも、健全な思考にとっては。
「独学」というキーワードがついた本で、他者との対話が語られていることは、非常に興味深いことのように思われる。あるいは、一昔前では「当たり前」だったそうしたものが、現代では失われつつある一つのあらわれなのかもしれない。