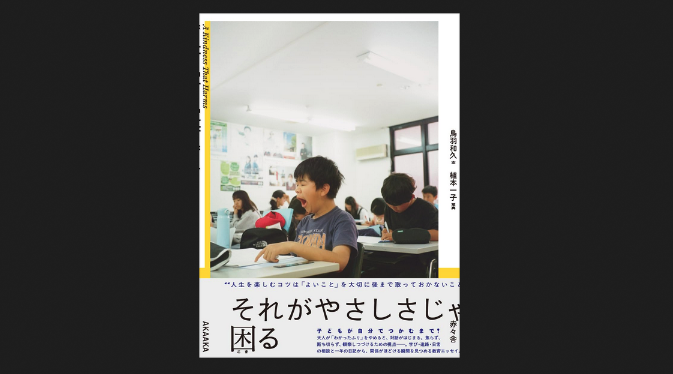タイトルの英訳は、”A Kindness That Harms”。ちょっとドキッとする言葉だ。
ある種のやさしさが、ときに人を傷つけてしまうことがある。損なってしまうことがある。40年以上も生きていれば、痛みを覚えながらそうした経験を思い出すことは一度や二度ではない。
本書が中心的に扱うのは、親と子ども(あるいは教師と子ども)の関係だが、その射程はもっと広い。たとえば、私は「管理する人」──つまりマネージャーの文脈で本書を読んだ。そう、「それがマネジメントじゃ困る」という出来事は多いのだ。
たとえばこんな箇所がある。
適切な声掛けというのは、確かに簡単なことではありません。スポーツの監督やコーチを考えればわかりやすいのですが、相手の動きを精細に観察することなしに、適切さを担保することは不可能です。
にもかかわらず、巷のビジネス書では「正しい声掛け」のノウハウが提唱され、それを学んだマネージャーたちは、相手を観察することなく「正しい手順」をなぞろうと必死になる。そこでは、具体的な人への眼差しや、その声を聞こうという構えがまったく欠けている。
本書はその意味で、徹頭徹尾「人間」を見つめるための手引きである。
目次は以下の通り。
- 第一章 学校 : 子どもは高度な表現者
- 第二章 親と子 : 安息の場所
- 第三章 勉強 : 「学び」に巻き込まれる
- 第四章 受験 : 「進路選択」という無理難題
- 第五章 お悩み相談室 : 毎日新聞EduAより
- 第六章 やさしさと配慮 : 放っておいてくれた人
著者は子どもを人間として見つめ、接している。そこにあるのは四つの特徴だ。すなわち、個別的・具体的な存在、内的な力を持つ存在、関係の中に置かれる存在、変化していく存在として、相手を捉えること。
単純なレッテル貼り(勉強ができる子、いじめっ子、暗い子)によって情報を処理すれば認知は省エネかつスムーズに進んでいくが、それぞれの人の個別性・具体性はまったく目に入らなくなる。それでは手段は空回りするだろうし、それ以上に相手の尊厳を傷つけることになりかねない。
逆に、それぞれが固有の存在であることを受け入れるなら、そこに内的な力がありうるだろうことも想像できる。子どもは無力ではないし、むしろ著者が言うように高度な表現者であろう。相手を無力な存在だと思い込むなら、私が導かなくてはと手を引く力が強まってしまう。それがときに害を為すことは想像に難くない。
だからといって、人間はただ存在しているのでもない。私たちは(広い意味での)環境や関係の中に置かれ、その中で振るまいを生成している。内的な力がどう発揮されるのかは、”意志”だけで決まるものではない。むしろ意志(というかやる気)のような曖昧なものに働き掛けるよりも、まず環境や関係を見直した方が良いことは多いものだ。
そして人は、そのような環境に晒されながら、時間と共に変化していく。今目の前に見える姿が、永久に続いていくのではない。人が生きることはプロセスであり、そのプロセスの先にある姿は、一介の人間には見通せない。そのように認識することは、人間存在を信じることであり、あるいは未来に希望を抱くことでもある。
本書全体を通して、私は著者のそうした眼差しを感じた。その眼差しは、子どもだけに向けられるものではなく、子どもに寄り添う親にも向けられている。敷延すれば、先ほど述べたように上司と部下の関係にも向けうるものだろうし、もっと言えば「自分と自分」の関係にも向けられるように思う。
私は、私にやさしくできているだろうか。
現代において問うべき価値のある自問かもしれない。