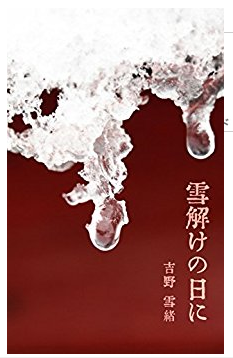故郷への想いと、都会(東京)への思いが、決して交じり合うことなく同居している。都会に染まりきれないもどかしさは、でもそれがアイデンティティーの一部でもあって、やり場も行き場もない感覚を生じさせる。
そんな不確かで、捉まえようとするとスルりと逃げてしまう感覚を、リズムのよい言葉の断片で描いている__という風に感じた。正直詩歌集というのを読んだのすら初めてなので、自分の感想が的を射ているのかすらわからない。でも、心地よいことはたしかだ。
「前職」より。
橋をかけている
文章で
Scriptで
向こう岸に戻るための
橋をかけている記す経歴あるでなし
ひとりコミットログを積む
語るでもなく語る。綴るでもなく綴る。微妙な距離感なのだ。突き放すでもなく、かといって自我に溺れるのでもない。ぎりぎりの自嘲と皮肉。しかし、決して消えていない希望。
「二律背反」より。
やすらげてひとり
声をわすれる憎し憎しとだれかをのろい
とたんにあふるる言葉かな
実感を伴ったそれは、岩を穿つ水滴のように染みこんでくる。断片であるがゆえに、飛躍が許容され、入り込む隙間が生まれる。そのような体験は、やはり詩ならではと言えるだろう。
加えて言うならば、コード書きが詠む歌、というだけで単純に興味深い。どんな言語作用がその背景にあるのだろうか。人間の脳とは面白いものである。
▼目次情報:
新年
労働
雪について
文人に寄す
東京
1LDKの慟哭
酒について
愛について
熱海行
郷土の四季
あとがき
Tags: