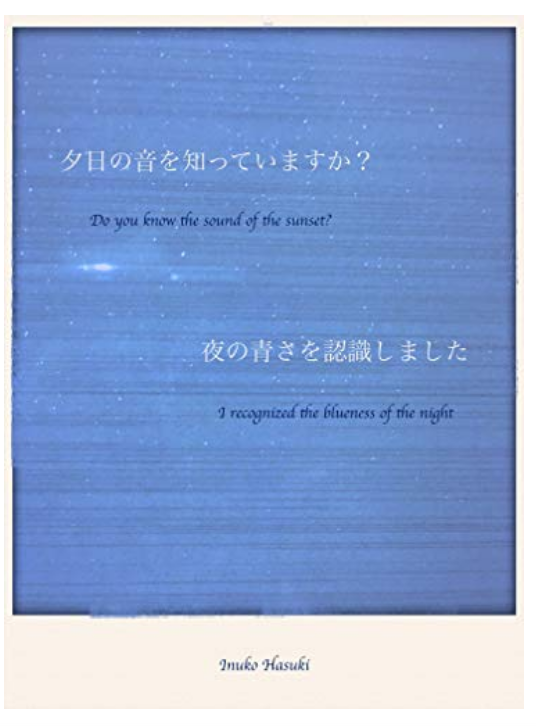人間がいなくなった学術都市ワースレスガーデン。その街の図書館を管理するのは少年型ロボットのクゥクゥ。彼の元に、かつてこの街に住んでいた女性ゼラが訪れる。彼女は、クゥクゥをこの街から連れ出すという。この街を管理する役割を持つクゥクゥは、それはできないと断る。そんなことがしたいとも思わない。
ゼラはやがてプログラミングをはじめる。人工知能に関するプログラムを。
彼女はパンドラの箱を開けようとしているのだろうか、それとも開けられてしまった箱を閉じようとしているのだろうか。
■
物語の序盤は、少しつかみ所がない。わかりにくい日本語が並んでいるわけではないのだが、凹凸が見えにくい。目が悪い人がロッククライミングにチャレンジしている感じだろうか。しかし、一度その儀式を通過すると、驚くほど滑らかに物語は流れていく。不思議な体験だ。
たぶん、それは著者の意欲的な試みが関係している。
文章を読むという行為は、脳内に情報空間を立ち上げる行為である。読み手は、著者が示した文字情報を手がかりにその空間を立ち上げる。ただ、物語の序盤では情報が少ない。普通はそれを補助するためにさまざまな情報をそれとなくちりばめるものである。「三人称壁視点」では、それが意識的に抑制されている。だから、脳内に情報空間が立ち上がりにくいのだ。
しかし、一度それができあがれば、つまり私の脳内でクゥクゥとゼラが立ち上がれば、あとはこちらのものだ。モノローグがない分、恐ろしくスムーズに物語が流れていく。それでいて欠落を感じることはない。だって、もう私の脳内にはクゥクゥとゼラがいて、クゥクゥが不器用そうに笑う映像や、ゼラがぶつぶつ言いながらプログラミングに打ち込むシーンが浮かんでくるからだ。
そのクゥクゥやゼラは、著者が脳内に描いていた二人(クゥクゥもひとりと数えて良いだろう)とは異なるだろう。他の読者が描いたそれとも違っているだろう。それでいて、そこには共通の何かがあるはずなのだ。それが文章作品の素晴らしいところであり、映像作品では起こりえない現象でもある。
本作はテーマ的にも面白いが(ロボットにとって「本当の自分とは何だろうか?」)、それに加えて新しい表現にチャレンジして、新しい読書体験をもたらしてくれる点も興味深い。
森博嗣も『作家の収支』も中で次のように述べている。
新しさを生み出すこと、新しさを見せること、それが創作者の使命である。
新しければいいというわけではないが、その追求をやめてしまったら、そこが行き止まりになるだろう。