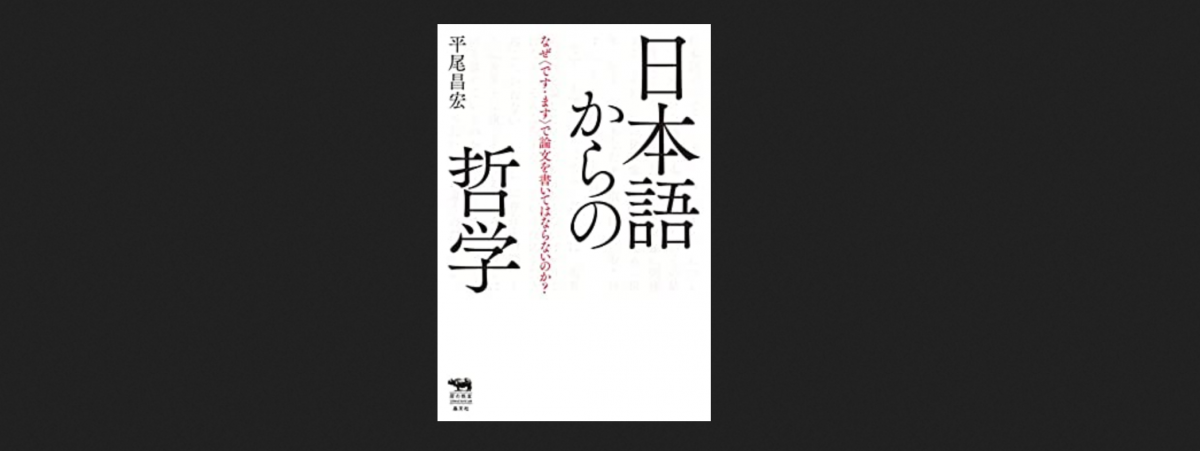本書は非常に面白く読めた。それは最近の私のチャレンジが関係している。「実用書を常体で書く」というチャレンジだ。
これまで私が書いた本、特に実用書・ノウハウ書に分類される本はすべて敬体つまり、「ですます体」が使われている。意図的な選択がそこにあったわけではない。「なんとなく」というか、まわりの本がそうだったから、というのが近い。それに「だ」や「である」を使う常体は、なんだか偉そうな感じがする。仕事を始めたばかりのペーペー物書きが使っていいものではない、という雰囲気もあった。結局それ以降も──力強い惰性によって──、「ですます」を使いながら実用書を書いてきたのだが、最近になってこれを変えたくなった。つまり常体を使いたくなった。
なぜだろうか。
自分では、その理由について明確に言語化できていなかった。ただし、意図として変化を求めていたことはたしかだ。文章のリズム以上の変化、言い換えれば、コンテンツの在り様の変化を求めて、文体を変えたがっていた。
本書を読み終えて感じたのは、きっと私は「距離」を変えたかったのだろう、ということだ。書き手と読み手の距離、あるいは関係を。
たしかに「ですます体」は丁寧な雰囲気がある。何かの情報を教えるコンテンツの場合、サービス業のような姿勢を持てば好感を持ってもらいやすいだろう。少なくとも、偉そうだとはねのけられる可能性は低い。さらに、本書の視点を借りれば、「ですます体」は読者に向かって語りかける構図(世界)を構築してくれる。その親密な雰囲気は、信頼感を勝ち取り、述べたことを信頼してもらう上でも有用に違いない。
とは言え、それはどこまでいっても「教師と生徒」という枠組みを超えてはくれない。書き手である著者が情報の保持者であり、読み手である読者はその情報の受容者である。
しかし、実用的コンテンツ、特に知的生産の技術やタスク管理といったものは、個々人の状況に応じて自分でアレンジして運用していく必要がある。それぞれの人が、自分のマスターになること。それが肝要なのだ。
「ですます」的な世界は、丁寧に情報を伝えようとするのに効果的である反面、読み手を読み手のままに留めてしまう可能性があるのではないか。それはもしかしたら袋小路なのかもしれない。
対して、「である」的な世界は、著者が指摘するように読み手と書き手は共同の場に所属する一員として認識される。いつでも、同じ土俵で、論文を書く人になる、という前提が(あるいは期待が)そこにはあるのだ。
そうすると、実用的コンテンツにおいて必要な世界は、実は後者ではないだろうか。読み手は「お客様」ではない。本を読み終えたら、実践を始める主体者である。つまり、書き手と同じことをする人間なのである。
■
本書では、「ですます体」とそれが構築する世界が切り開く可能性が提示されている。そういう書き方しか、表せないものがあるのではないか、という視点だ。たしかにその通りであろう。
一方で、私は逆に「である体」とそれが構築する世界が、まだ十分に使われていない分野もあるのではないかと思う。「ですます」体とは違った形で読み手を鼓舞するコンテンツの在り方。それはそれで追求する価値があるように感じられる。
というわけで、本書は文体(あるいは文末)への注目からはじまり、そこから文章の在り様へと展開して、最後には全体的な物事の捉え方へと展開していくエキサイティングな哲学書である。
単に「ですます」や「である」をどのように使い分けるか、という話ではなく、どのような世界をそこに立ち上げていくのかを考える上で有用な議論を提供してくれている。