結局のところ、問いは一つに集約される。ウィンストン・スミスは、不幸になったのか。それとも幸福へと誘われたのか。
答えを出すのは簡単ではない。
あらゆるディストピアは、ユートピアでもある。人間にとっての楽園を目指して行進すると、辿り着いた場所は地獄だった──ディストピア小説によくある構図だ。では、逆は言えないだろうか。徹底的なディストピアは、ユートピアと変わらないのではないか。
もちろんそれは可能なのだ。人は、二重思考の片側でユートピアを生き、もう片側でディストピアを生きることができる。なんたる幸福=苦悩だろうか。
本作は、超有名な「ビッグブラザー」が登場する作品であり、全体主義への批判の書としても、「政府」が歴史を改竄し、情報を改変しているというまるで現代的な状況をも指摘する本としても扱われている。トランプ大統領の登場で、本書が再び注目されているのもわからないではない。しかし、そのブームこそがまさにビッグブラザー的であるのは皮肉にしてもあまり笑えない。そこに宿るのが憎悪であるならば、コインの表裏に差はないのだ。
本書はディストピア小説ではあるが、かといって本書のテーマがディストピアにあるのかはわからない。そんなことを言えば、私たちの生そのものがディストピアだとも言えてしまうのだ。むしろ本作は、ひとりの人間の「生きること」こそがテーマであるように思える。もちろん、舞台装置は大がかりであり、それだけでも十分に鑑賞に値する。見事なものだ。
しかしビッグブラザーはどこにもいない。それは純然たる偶像であり、空っぽのイデアなのだ。そんなものは世の中にごまんとある。たまたまそのうちの一つが、特異点的に力を持っただけにすぎない、という見方もできる。となると、問われているのは、「そんな中でどのようにして生きるのか」という姿勢になるだろう。そして、それこそがすべてだとも言える。
そのようにして背景装置をすべてフラットにしてしまえば、本作は恋愛によって逸脱した男が辿る人生の物語のようにも読める。彼はそのまま生きることもできたし(できなかったし)、逸脱し続けることもできた(できなかった)。選択とは言えない選択があり、抗えない状況と情熱があった。
一体全体、「人生を豊かに生きる」とはどういうことだろうか。そして最初の問いに舞い戻る。ウィンストン・スミスは、不幸になったのか。それとも幸福へと誘われたのか。
答えを出すのは簡単ではない。
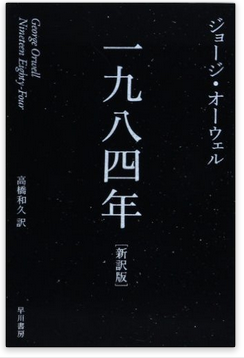
![一九八四年[新訳版] (ハヤカワepi文庫)](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/41ZAgdWin2L._SL160_.jpg)








One thought on “『一九八四年[新訳版] 』(ジョージ・オーウェル)”