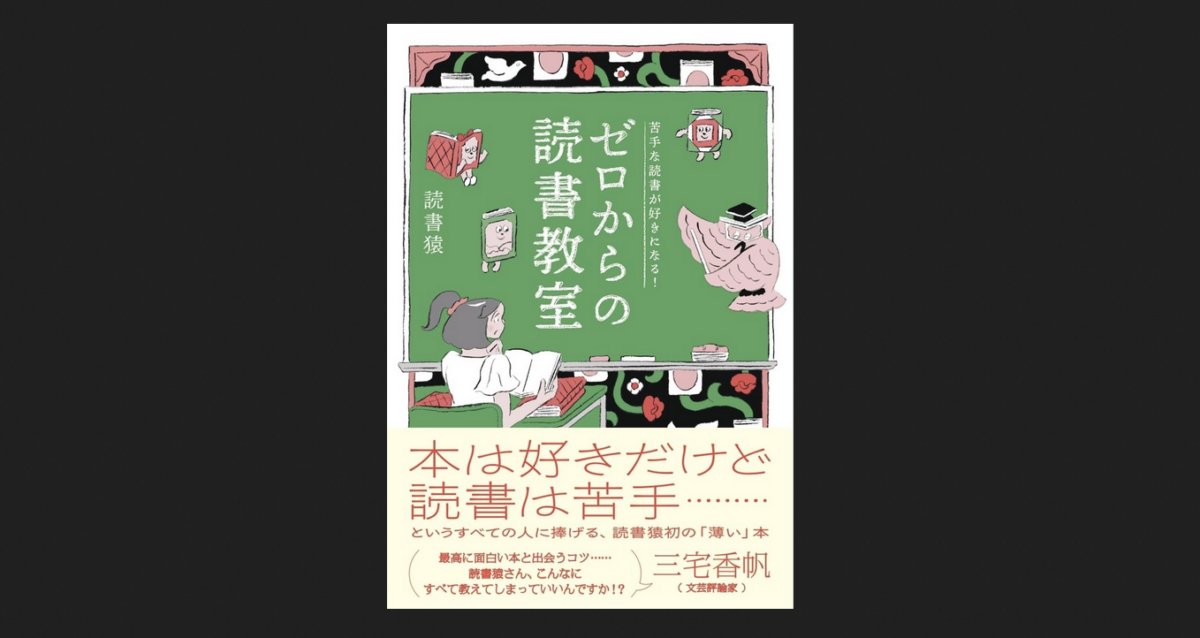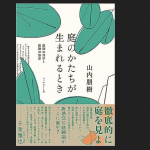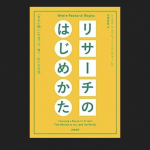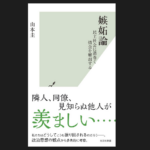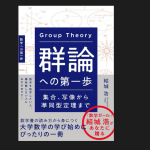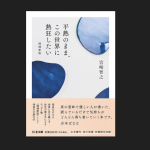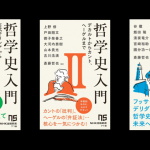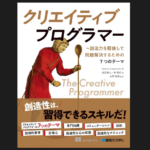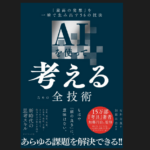本を読むのが苦手だ、と思ったことがない。その意味で私は本書の良い読者ではないのだろう。
であれば、本書から得られるものは何もないのかというとそういうわけではない。むしろ、ああ、たしかに自分はこうして本を読んでいるな、と自分でも意識していなかったことが確認できた点は大きい。
毎日のように本を読んでいると、そこで細かい技法の使い分けを行っていることすら意識に上らなくなってくる。それらを一緒くたに「本を読む」と表現してしまうのだ。これでは人に本の読み方を伝えるのは難しい。
本書では──私のような大雑把な認識ではなく──、より個別的・具体的に本を読むことを腑分けしていく。その手つきはきびきびしていて見ていて気持ちがよい。「読む」とはどういうことかを観念的にではなく、方法的に読み解いていく所作は職人芸のようである。
目次は以下の通り。
第1部 本となかよくなるために……しなくてもいいこと、してもいいこと
第1回 全部読まなくてもいい
第2回 はじめから読まなくてもいい
第3回 最後まで読まなくてもいい
第4回 途中から読んでもいい
第5回 いくつ質問してもいい
第6回 すべてを理解できなくてもいい
第7回 いろんな速さで読んでいい
第8回 本の速さに合わせてもいい
第9回 経験を超えてもいい
第10回 小説なんて読まなくていい
第11回 物語と距離をおいていい
第12回 小説はなんでもありでいい第2部 出会いたい本に出会うために……してみるといいこと、知っておくといいこと
第13回 いろんな本を知ろう
第14回 本の海「図書館」へ行こう
第15回 レファレンスカウンターに尋ねよう
第16回 百科事典から始めよう
第17回 百科事典を使いこなそう
第18回 書誌はすごい道具
第19回 書誌を使ってみよう
第20回 件名を使いこなそう
第21回 上位概念を考えよう
第22回 リサーチ・ナビを活用しよう
第23回 青空文庫に浸ろう
第24回 デジコレにもぐろう
第1部は本を読むことに焦点が当てられ、第2部では本の探し方が解説される。
個人的に面白かったのは第1部で、最初は本を読むことの話をしていたはずなのに、気がついたら文章を書くことの話にスライドしている。でも、それはそうなのだ。文章を書くことと文章を読むことはつながっている。文章は、読むために書かれるからだ。だから書き方を知っていれば、読み方にも詳しくなる。天才的な犯人が、天才的な探偵と通じ合っているように。こんな自明の話も、読書のノウハウでは語られないことが多い。
ちなみに、読書における問いとミステリーの話が出てくるが、以前オンラインの読書会で似た話題が出てきた。読書メモの書き方は人それぞれで異なるから統一的な話がしにくいが、「犯人を当てる」タイプのミステリー小説を読むときは、何を問うているのかが共通しているので皆でメモの書き方について話し合うことができる、といった話だ。
読書のメモの書き方の練習には推理小説がよいかも、というアドバイスなんか誰にもされないだろう(これは私がそう考えているだけだが)。世の中にはまだなされていない読書のアドバイスがいっぱい眠っているのである。しかし、読書を高尚なものに位置づけ、それ以外の目的を無視してしまえば、そうしたアドバイスも眠ったままになる。残念なことだ。
さいごに
というわけで、本書は「本の読み方? そんなの一つしかないだろう」と思っている人が、読書という豊かな行為と出会い直す手助けをしてくれる一冊である。二人の登場人物(フクロウと女の子)の対話で進んでいくのでスピーディーに読めるし、会話のユーモアが楽しさを盛り上げてくれている。中高生向けではあるが、私たち大人だって知らない分野の知識はみな中高生レベルであることを考えれば、文句無く「読書が苦手」な大人でも役立つ本である。
ところで繰り返すが、私は「本を読むのが苦手だ」と思ったことがない。むしろ、多くの人は「本を読むのが苦手だ」と誰か(何か)に思わされているのではないかと思うが、いかがだろうか。