梅棹忠夫の業績を振り返った本はいくつも出版されているが、本書はタイトルにもあるように、予言者としての梅棹に注目している。
とは言え、彼の先見性を称えるのではなく、その「予言」がいかにしてなされたのかに注目した上で、同じ視点を持って現代を眺めようという意図がある。面白い着目点だし、必要でもあろう。
目次は以下の通り。
- プロローグ 実現した予言と失われた時代
- 第一章 「文明の生態史観」の衝撃
- 第二章 モンゴルの生態学者
- 第三章 奇説を語る少壮学者
- 第四章 豊かな日本という未来
- 第五章 情報社会論の先駆者
- 第六章 イスラーム圏の動乱を予告する
- 第七章 万博と民博のオーガナイザー
- 第八章 文化行政の主導者へ
- 第九章 ポスト「戦後」への視線
- 第十章 行為と妄想
- エピローグ 梅棹忠夫を「裏切る」ために
ご覧の通り、学問的な業績や「知的生産の技術」のアジテーターとしての側面は薄い。その代わり、行為者として、もっと言えば彼が社会とどうコミットしてきたのかに注目が当てられている。むろんそれは、その射程を現代から未来へと伸ばすためでもある。
梅棹の歴史については、本書で特筆する何かが上げられているわけではない。そのあたりは、『行為と妄想』をあたりを一読すれば十分だろうという感触はある。ただし、第9章、第10章の著者の視点は厳しく、鋭い。
九章の終わりで著者はこう述べる。
そして梅棹忠夫は、日本文明がもはや順調に文明史曲線をたどることはありえないと思い始めていたのだから、物質的な文明が豊かさをもたらし、文化と呼ばれる精神性はその投影に過ぎないと考える文化・文明論を根本的に見直す必要があった。日本文明がこれからも存続するには、「精神のキバ」を生やすべきだと強くいうべきだった。
同意したい気持ちもあるが、それを梅棹に求めるのはあまりに酷ではないだろうか、という気もする。もっと言えば、甘えすぎているのではないか、とも。
たしかに文化が文明の投影でしかないのなら、豊かな「装置」をあまた所有する私たちは、安寧に眠り、キバを持つようなことは起こりえないだろう。しかしもし、文化というものが先駆して、文明発展の方向に影響を与えうるならば、今からの私たちでも遅くはないと言えるだろう。これから新しい文化を築いていけばいいのだ。ポスト・梅棹の世界において。
それはまちがいなく長い戦いになるだろうし、苦しい戦いにもなるだろう。世間の風はまったく逆に吹いている。しかし、である。失明後の梅棹の心境を想像してみると、一体それがなんなのだ、という気持ちになってくる。私たちはまだまだ活発に行動できるし、知的生産を行えるし、いろいろなリンクを築いていでいくことができる。文化を築いていくことができる。
「情報化社会」なるものが一体何なのかは曖昧模糊としているが、もしかしたらそれは人類史上初めての社会なのかもしれない。その社会においては、文化は文明に先駆しうるかもしれない。そのような存在は、文明という長いスパンを持って社会の推移を的中させてきた「予言者」であっても見通せなかった可能性がある。その可能性は、とりあえず希望という言葉でラッピングしておいてもよいだろう。
一つ懸念されるのは、現代の言論人において、梅棹のような長いスパンを見据えた上で社会を論じている人間があまりにも少ないことである。せいぜいここ50年、悪ければ数年単位の話しかしない。このような視点は、小さい変動に誤魔化されて、長期的な予測を見誤ってしまう。
「今日株価が下がったから、この企業の10年後には価値がない」、なんていう人間には耳を傾ける価値はないだろう。しかし、言論人の多くはそれと似たり寄ったりなことを言っている。多すぎるノイズに惑わされているのかもしれない。あるいは、そうした言論人が見受けられないこと自体が、戦後日本の文化的欠落を意味するのかもしれない。
2016年に出版された『サピエンス全史』はどっしり構えた視座を提供してくれたし、他にも似たような海外の著作はある。しかし、日本はどうだろうか。そのような射程で何かが論じられ、広く読まれるようなことがあるだろうか。やはり、長く苦しい戦いになるのだろう。
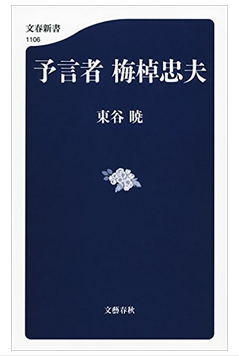









One thought on “『予言者 梅棹忠夫』(東谷 暁)”