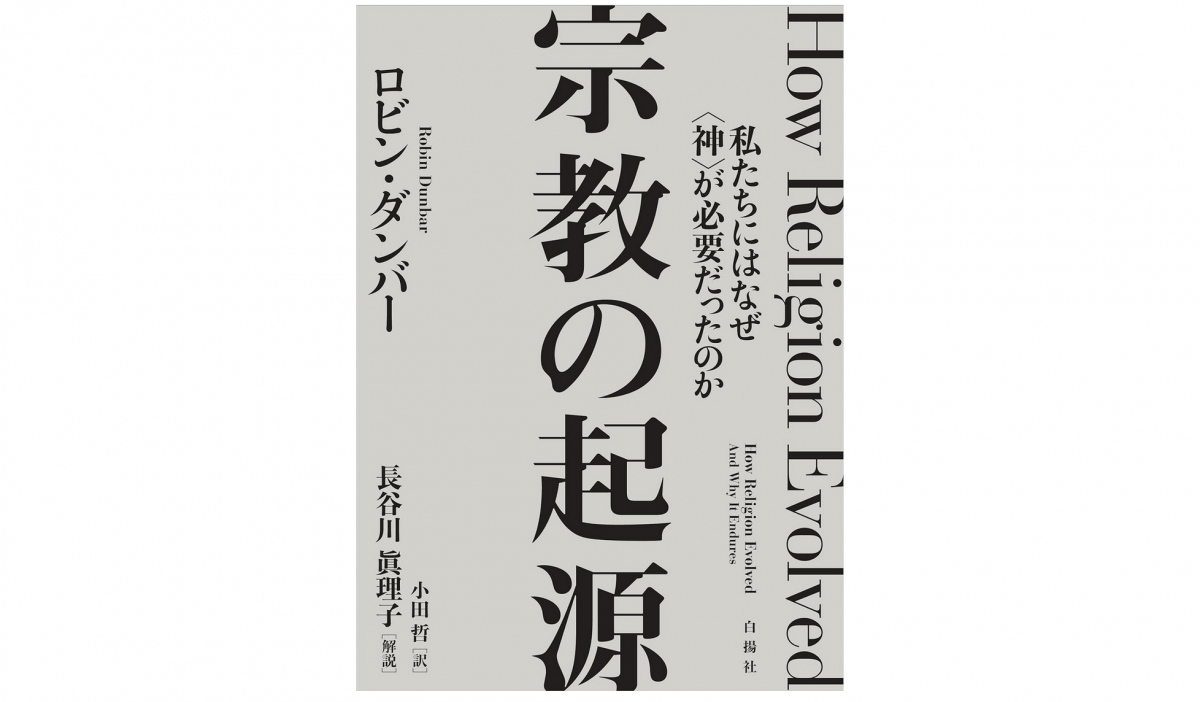あのダンバーが宗教の起源に迫るというのだから読まずにはいられない、と思っていたら出版社さまからご恵投いただいた。ありがとうございます。
さて、日本だと「宗教」はうさん臭く見られがちだが、人類が共通して持っている文化であることは間違いない。日本だって一神教的な「神」は信じられていない代わりに、やたらめったら神が見出されている。スピノザとは違った意味で、神は人類の中に遍在しているわけだ。
気になるのは、なぜ人類はそんなに普遍的に宗教を持つのか、ということ。さらに著者は、そうした宗教がなぜこんなにバラバラなのかという点も気にかけている。たしかにそうだ。あたかもバベルの塔が壊されたみたいに世界中には多様な宗教がある。同じ宗教内であっても宗派が分かれていて、結構不穏な空気を呼ぶことも珍しくない。
普遍的であり、多様的である宗教。
そうした宗教は人類にどのような影響を与えてきたのか。人類学者ダンバーならではの視点で探求が進められる。中心になるのは進化論的な観点だ。簡単に言えば、人類の生存において宗教が機能したからこそ、今まで必要とされてきた。ではどのように宗教は機能したのか。いくつもの観点が検討されるが、注目したいのが「神秘志向」と「共同体維持」の二つの観点だろう。
まず後者から見ていくと、人間は単独では弱っちいわけだが集団だと力を発揮する。身を守るために集団化する動物は多いし、人間はさらに協力的に仕事を為すこともできる。ただし、問題がある。人が”仲良くなれる”数には限界がある。その生物学的上限を示したのがまさにこのダンバーであるわけだが(参照)、たくさんの人が集まると、どうしても人間関係がギクシャクしてくる。問題も起こる。そのとき、結束を強める何かを持っていれば、生存に有利だろう。そう、それが宗教という”道具”だったわけだ。
この観点は、現代において「宗教」というものを見つめる点でも有用だが、それ以上にこのグローバル社会の中で、多くの人々との接続を迫られている私たちの生活を考える上でも有用性が高い。私たちは何の”道具”もなしに、そんなにたくさんの人間と仲良くなれるわけではないのだ。少し前は「トライブ」なんて言葉もあったが、何の仕掛けもなしに維持できる集団の規模はとても限られている。
そう理解して、世の中で成功している「集団」を見ると、宗教そのものではないにせよ、そこでは儀式的なものがうまく利用されていることが見えてくる。ちゃんと仕掛けがあるわけだ。
この理解をどう使うかはそれぞれの人次第だろうが、そういう実用性を抜きにしても面白い話である。
で、前者の「神秘志向」だが、ほとんどの宗教は何かしらの神秘志向を持つ。超自然的というか、私たちの意識では捉えきれない何か大きなものがこの世界に影響を与えており、宗教的な活動はそれに関与する、という感じだろうか。これも実に人間的な話で、AIはまったく経験しないことだろう(彼らが何かを”経験”するのかも不明だが)。
そうした神秘体験はトランス状態と結びついていて、そこでは「生身の感情」を感じられるからこそ、私たちにとって宗教は非常に力強く作用する。理性的・規範的なものを取っ払って、「本当/真実のもの」に触れられる感覚があるからこそ、「私は世界の真実を知った」という感覚に至れるのだろう。
でもって、現代は理性的・規範的な力が強まっている時代である。特に外部からもたらされるそれは、インターネットの力を借りて年々増幅している気すらする。そうした環境では「生身の感情」から遠ざかってしまうことは間違いなく、その反動として宗教的なもの、もっと言えば、トランスをもたらすもの全般がより強く希求されるに違いない。たとえそれがどれだけ危ういものであっても(あるいは危ういものだからこそ)、求められてしまうのだ。
その意味で、トランス状態を起こすものを徹底的に疎外するのではなく、むしろ日常の中に──できるだけ害が限定された形で──取り込んでいく方が人間としては健全なのかもしれない。別にドラッグをキめる必要はなく、こうして一心不乱に文章を書いているときでも私はちょっとトランスしている気がする。そういう健全なトランスは、人類が人類として必要としているのではないだろうか。
といった具合に、宗教についての興味もさることながら、「人間とはどのような生き物なのか」を考える上でも非常に面白い本であった。