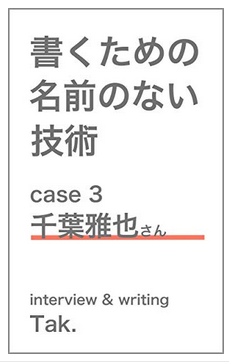『書くための名前のない技術』シリーズ第三弾。今回は哲学者の千葉雅也さん。
まず、この組み合わせで面白くないはずがない、という予想が立つ。そして、その予想をゆうに3倍は上回ってくるのが本書である。
中身についてはR-styleで触れるとして、今回はシリーズ物としての観点から本書を眺めてみる。
■
「書くための名前のない技術」シリーズは、タイトル通り「書くための技術」を扱うコンテンツである。そして、──やはりタイトル通り──それが「名前のない技術」であることが特徴でもある。「技術」としてはなかなか認識されない、「あえて」は取り上げられないものを、あえて救い上げようとする。そのような試みが本シリーズだと言えよう。
その観点から見たとき、本書はいささか奇妙に映る。それはインタビューの対象が著名だからではなく、「書く技術」について極めて自覚的であるからだ。本書では、確立された(そして変化の期待もはらむ)方法論がきちんと提示されている。対話の中で「そんなことが大切だと思わなかった」という新しい発見が次々と起こるというよりも、「やっぱりそれって大切ですよね」という同意、あるいは共感の方がずっと多い。あえて救い上げなくても、すでに素材はそこに並んでいるのだ。
その意味で、私の予想にすぎないが、本書の「Part 2」は非常に書きにくかったのではないか。ポイントはすでに当人によって語られてしまっているからだ。もちろん、「Part 2」が蛇足というわけではない。再確認・復習の意味もあるし、読者が気づかなかったポイントを提示してくれている効能もあるだろう。それでも、本書の「Part 2」は、全二作の「Part 2」とはやや色合いが異なるように感じる。そのことに是非はない。単に、違って感じるだけである。
■
とまあ、ごちゃぎょちゃ書いてみたが、同じシリーズなのに、case 1〜3までここまで異なった雰囲気になるのか、というのが一番の驚きである。テーマは同じ、聞き手も同じ、構成も同じ。しかし、三作からはまったく異なった雰囲気を受ける。それは、聞き手としての著者があまり前に出過ぎないようにしている(≒語り手の個性が出やすい)という点と、たとえシリーズ物であっても無理に雰囲気を統一しようとしてない自由さから生まれているのだろう。
なにしろアウトライナーとは、アナーキーな存在なのである。
それを実行した瞬間に元のアウトラインが変わる。型からこぼれたものが型を変えてしまう。アウトラインは秩序や権威を感じさせるけれど、アウトライン・プロセッシングはアナーキーなんです。
— Tak. (@takwordpiece) January 31, 2020
シリーズという「型」を作りつつ、内容に合わせてそこから逸脱し続けること。アウトライナーフリークの著者たるシリーズ構成だと言えるのではないか。