2016年で、もっとも重要な一冊と言ってよいだろう。
タレブの『ブラック・スワン』、カーネマンの『ファスト&スロー』と並んで、個人的必読書の一冊である。ちなみに個人的必読書とは、明日私が記憶喪失になることが決定しているとき、その明日の私に対して送る「この本は読め」リストに掲載される本のことだ。人生をもう一度繰り返すとしても、読みたい本と言い換えてもいいだろう。
本書は、たいへんどっしりと構えた本である。人類のこれからの未来について考えるために、そもそもの人類の起こりから話を始めている。複数のサピエンス類が地上に存在し、なぜかその中でホモ・サピエンスだけが突出して繁栄した。それはなぜか?
著者は、その理由をホモ・サピエンスだけが大きな集団を作ることができたからだ(そして、火を使うことができたからだ)と説く。それを支えたのが認知革命である。認知革命は、私たちに二つのものをもたらした。一つは、虚構を生み出す力。そして、それを信じる力だ。
この世に存在する≪システム≫は、そのほとんどが実体を持たない。会社も、宗教も、国家も、貨幣も、虚構なのだ。私たちはそうした虚構によって結びつけられ、社会を運営している。私がコンビニで買い物をして1000円札を出すとき、店員はそれが自分が提供する商品と同等の価値を持つのかどうかをいちいち疑わない。それは貨幣という虚構を信じているからであり、それは貨幣を提供する国家を暗黙に信頼しているからである。
この社会が(多少の例外はあるにせよ)滞りなく運用されているのは、まさにこの虚構と信頼の力なのだ。人類の文明は虚構の上に立脚している。
間違えてはいけないのは、ここで虚構の意義を否定することだ。虚構という日本語には「嘘っぱち」という否定的なニュアンスがあるが、実際それらの虚構がこの世界から消えてしまったら、私たちの社会はあっという間に機能不全に陥ってしまうだろう。虚構は、少なくともこの社会を成り立たせていくために必要なのだ。
しかしそれは、実体がないが故に非常に危ういものでもある。皆が信じている間は、鎖のような束縛力を持つが、ひとたび皆が信頼を放棄すれば崩れさってしまう。虚構は脆い。が、それは変化の可能性をいつでも含んでいるということでもある。『ソードアート・オンライン』や『アクセル・ワールド』シリーズの言葉を借りれば、シンイで上書きできる可能性があるのだ(※)。
※川原礫の両作品は、この点からきちんと評価されるべきだろう。
とは言え、一つの決定を下さなければいけない。現実の≪システム≫を上書きするとして、それをどちらの方向に進めるのか。それが本書がラスト2章で提起している問題でもある。
私たちホモ・サピエンスは、神の寵愛を受けてこの地上で繁栄してきたわけではない。認知上の特異な機能を持ち、それが大集団を構成するのに適していたから、今このような状態になっているのだ。
農業革命と科学革命を経て、地球上には人類が溢れかえっている。その代わりに、生物種の数は著しく減少した。皮肉なことに、人間の食用となるニワトリはとんでもない数になっている。地球の生態系が、人類が生き延びるように「デザイン」されていると言ってもいい。しかし、それは人類の特権ではない。
もし、認知上の特異な機能を持つ新たなサピエンスが登場したら、私たちは退場を余儀なくされるだろう。そんなことはとても起こりえないように感じるかもしれないが、きっとネアンデルタール人だって同じように感じていたかもしれない。所詮私たちは、サピエンスの一種でしかない。そして、種の交代はいつだって起こりうるし、むしろホモ・サピエンスが自らそのトリガーを引くことだってありうるのだ。
私たちは、虚構によって連帯をつなぎ、巨大な集団を支えてきた。「大きな物語」は、ホモ・サピエンスと共にあったのだ。しかし、それが最近では崩れてきている。過去を支配してきた神話が、機能不全を起こし始めているのだ。
皆が共有する物語の中で個々人の期待が発生し、その期待が裏切られることでヒトは自らの不幸を規定する。だからこそ、人々は「大きな物語」を拒絶し、フィルターバブルの中で小さく閉じこもろうとする。その小さな物語の中では、ヒトの期待が過剰に膨らむことはないからだ。むしろ、心地よい安寧がもたらされる。
さて、私たちはどちらに向かって進めばよいのだろうか。
全人類が再び共有できる「大きな物語」を復活させるべきだろうか。グローバリズムとコマーシャリズムの避けがたい融和は、貧富の格差を生み出し、それが個々の人々に不幸を植えつける。それを回避するためには、市場そのものを新しくしなければいけないし、それはつまり、貨幣という虚構から別の虚構へと乗り換えることにつながる。当然それは、貨幣を生み出し、それを支える国家からの脱却も意味する。私たちは、そのような方向に舵をとれるだろうか。
あるいは、連帯を拒絶した小さな物語で留まることを目指すべきだろうか。最終的には、それは誰ともつながらない世界へと落ち着くだろう。ヒトは、本当にそれで幸福を得られるのだろうか。
まったく別の舵もある。虚構を生みだし、それを信じる能力を持たない人類を作り出すのだ。そうすれば、今の人類が持ち合わせているありとあらゆる不幸は根絶できるだろう。なにせ、それを感じる力がないのだ。もちろん、その人類は私たちとは(見かけは似ていても)まったく違った存在となるだろう。彼らはきっと何も望まず生きていく。
本書は、「私たちは何になりたいのか?」ではなく「私たちは何を望みたいのか?」こそが真なる疑問ではないか、という言葉で結ばれている。
「ヒトは幸福であらなければならない」こともまた、絶対的な命題ではない。それは私たちが選択するものなのだ。

ユヴァル・ノア・ハラリ, 訳:柴田裕之 [河出書房新社 2016]

ユヴァル・ノア・ハラリ, 訳:柴田裕之 [河出書房新社 2016]
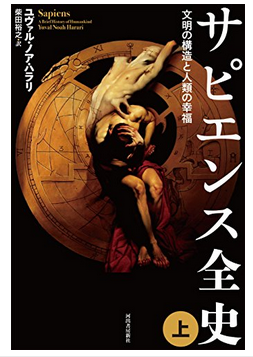
![ブラック・スワン[上]―不確実性とリスクの本質](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/41snE5NgDHL._SL160_.jpg)








