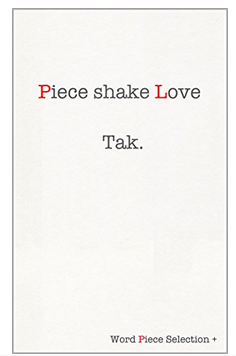京都から、東京に向かう間に本書を読んだ。
最初は在来線。混雑する日曜日の快速電車で、端の方に立ちながら__他にできることも特にないので__iPhoneで読んでいた。続いて乗り換えた新幹線。最高の読書タイム。ゆったりとページを読み進める。
不思議なほど、本書の読書は、在来線でのそれがしっくりきた。どこかに出かける人がいる。仕事に向かう人がいる。大人がいて、子どもがいて、カップルがいて、老人がいる。いろいろな声とも言えない声が飛び交い、視線が交じり合う。それぞれが距離感を気にしつつも、どうしたってパーソナルな領域は浸食される。お互い様だ。そして、窓の外では町並みの風景が流れていく。
そんな猥雑とも言える、それでいて一番現実に近しい風景に溶け込んで本書を読んでいると、ありありと浮かび上がってくる何かがある。その日私は出張であり、妻と一日以上離ればなれになってしまうのだが(決して大げさではない)、そのことが少し悲しく感じられ、またそう感じられることの暖かさも感じられた。そんな本である。
「なんともいえない」という感想は、こういう本のためにしっかりと秘密の箱にしまっておくべきだ。今回はそれを堂々と献上しようと思う。本書の断章感(断片感)は、たくさんの隙間を持ちながらも、そこに「確固たる説明」が入り込むことを拒絶している。あるいは、そのように感じられる。そのような説明がまるで無意味だとは思わないが__でなければ、この文章を書いている私は論理エラーで止まってしまう__、それでも全体を捕まえ切れるものではない。
言葉にならないことを、言葉によって伝えるためには、何かしらのトリックが必要なのだ。あるいは、それはトラップなのかもしれない。どちらにしても、本に夢中になる人にとって大差はない。
一応文体的な話をしておくと、本書の文体は初期の村上春樹さんのような匂いが感じられた。著者が意識したのかはわからないし、私が村上春樹過敏症なのかもしれないが、それでもそのリズムはなかなか心地よかった。
全体をひと言でまとめておくと、「いや、これすげーよ」である。いや、これすげーよ。