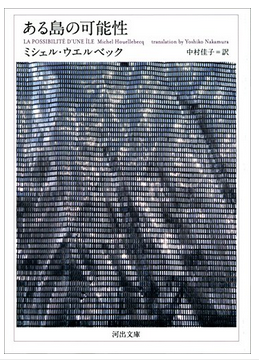改めて振り返ってみても、読了後の感覚をうまく言い表すことができない。そんな作品である。
ひねってはあるものの構成自体はシンプルだ。辛口コメディアンのダニエルの人生記と、彼を初代とするネオ・ヒューマンたちの日記が交互に綴られる。少し村上春樹さんの『世界の終わりとハードボイルド・ワンダーランド』を彷彿とさせるが、そこまでミステリー的な重み付けはなく、わりと早い段階で、なんとなく推測できる構図となっている。
であれば、この奇妙な読後感はどこからやってくるのだろうか。
本書で語られるダニエル(あるいはダニエル1)の物語は、人間の持つ愚かさと恐怖と快楽と絶望についての話であり、それはつまり文学の領域の話である。本作はそれを割愛することなくまるごと提出しながら、それをメタな視点で眺め、その上で「人類の次」についての世界を提示する。それはまったくもってSFの領域の話である。
つまり本作は、SF仕立てで語られる文学でもなく、かといって文学のフォーマットを借りたSFでもない。まず文学世界が一つあり、それを包括するようにSF世界が提出される。しかも、一見優位に見えるそのSF世界は、やはりどうしようもなく文学世界の影響を受けていることもついでに示される。たいへん入り組んだ構成なのだ。
もちろん、本作の妙は、辛口で理知的なコメディアンが、狂信的な宗教集団と関わりを持つ面白みにもあり(そしてそれは、文学とSFの架け橋にもなっている)、その点は現代のポピュリズムを眺める視点にもなるだろう。大衆を操作する力やその欲望は、極限まで振り切れば、人間そのもの、あるいは人類を操作するものへと近接してしまう。
ユーモアと性愛が失われた後、はたして人類は人類であるのか。そこにあるユートピア、は誰にとってのユートピアなのか。そして、私たちはどこに向かって歩こうとしているのか。
壮大な舞台装置を使って語られる本作は、見事と言うほかない。

ミシェル・ウエルベック 訳:中村佳子 [河出書房新社 2016]