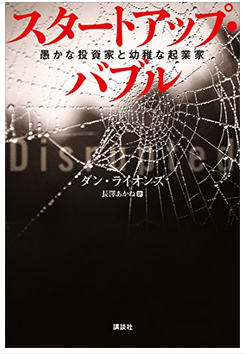なんとなく「IT企業のここがひどい」という話が陰鬱に展開される本かとタイトルから想像していたのだが、そうではなかった。本書の前半は、むしろ、IT化の波によって、会社を首になったおじさんが、なんとかして新しい職場を見つけ、その職場に馴染もうとする奮闘記として読める。
彼は、心の中で悪態はつくものの、基本的には相手の企業文化を尊重し、できるだけそこに馴染もうとしている。はなからバカにしているわけではない。そこは歴戦のおっちゃんである。はなからバカにすることこそバカのすることなのだ、ということは重々承知している。このあたりは、読者の年齢が高いほど著者に共感を寄せるだろうし、夢溢れる若者ならば、本書の舞台となるシリコンバレーの一企業の方に共感を寄せるだろう。どちらにせよ、まだ「異文化交流に起きるハプニング」という感じである。いくぶん、楽しいすらある。
しかし、少しずつ話の風向きは変わってくる。こうした企業が、理念や理想だけは大きく吹聴するものの、実はほとんど中身が無く、ただただ大手企業に買収されるかIPOを成功させることしか考えていない、という事態が明らかにされていく。驚いたのは、インバウンドマーケティングを提唱している会社が、頻繁に電話営業をかけていることだ。これが本当ならば、詐欺とはいかなくても、大きな欺瞞がその理念に含まれていることになる。理念は立派だが、数字がまだ付いてこないというのなら、まだかわいげがあるわけだが、そうでないのならば立派な確信犯である。理念を謳っていれば、それについていくるやつらがいるだろう、というわけだ。
結局著者は、さんざんな目にあって、会社を退職する。もともと、『ニューズウィーク』のITを担当していた記者である。仕事が見つからないわけではない。だから彼はその惨劇から脱出することができた。しかし、そうでない「おじさん」ならば、どうなっただろうか。それを考えると実に頭が痛くなってくる。スタートアップ企業はスタッフを安くこき使う。そこでも理念が活躍する。しかも嘘っぱちの理念がだ。しかしながら、その構図はほとんどまったく日本の企業にも見受けられるのだから、対岸の火事ではないだろう。そもそも、私がいたコンビニ業界もほとんど同じ構図をしていた。むしろ、ストックオプションなどの小さな夢すらないのだから、もっと悲惨かもしれない。
結局のところ、マルクスが指摘した時代から、経営者と従業員の利害は一致してない。経営者は自分の懐を暖めることに必死になり、そのために従業員を安く使う。ただし、普通の企業ではそれは後ろめたい行為とされる。あまりやってはいけないけれども、という留保がつく。しかし、スタートアップ企業では、それが認められている。むしろ礼賛されている。そこがおぞましいわけだ。『一九八四年』の世界と同じである。
さらに恐ろしいのは、そのような中身が空っぽで、理念に反することを自社で行っている企業を運営している人間にも、圧倒的なファンがたしかにいる、ということである。そこにあるマーケティングのテクニックは、たしかに本物なのだろう。
著者が語る内実がどこまで真実なのかはわからない。脚色もあるのかもしれない。しかし、電話で営業攻勢をかけていることだけでも事実なら、後は添え物みたいなものである。理念の中身が空っぽだ、ということなのだから。