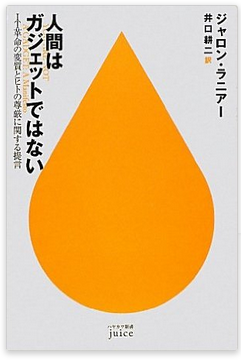著者は高らかに宣言する。
「人はガジェットではない」と。
もちろん私は問うことになる。「では、一体何なのか?」と。
著者は、次のように答える。
人であるとは、探求であり、神秘であり、根拠のない信念なのだ。
あまりに人間至上主義すぎるだろうか。そんなはずはない。むしろそういう「客観的」なものの見方が、私たちの生を貶めるのだ。
私は「私」として生きている。「私」を至上命題として、セントラルドグマとして、生きている。人間が人間に価値を置くのは、それと同じだ。そして、それこそがスタートラインなのである。それをはぎ取った思念は、実験室の中にしか存在しない。
私たちはまず人として生きて、その次に考えるのだ。その順番は決して逆にはならない。
人を定義するテクノロジー
我々は、テクノロジーを生み出す。マクルーハンに言わせれば人間拡張としてのメディアだ。
当然そのメディアは、「人間にとって〜〜が必要」という理念に裏打ちされて登場する。すると、気がつくだろうか。そこには、「人間」の定義が一片含まれてしまっていることを。我々は便利なモノ(ガジェット)を作り、そのモノによって、我々の定義がフィードバックされる。
これがコンピュータ以前の道具と、それ以降の道具が持つ影響の大きさの違いだ。「知」にまつわる道具は、返ってくるフィードバックがあまりにも大きいのである。何事も程度の問題という言い方があるが、まさにこれこそは程度の問題で、それが質的な影響にまで及んでしまう。人類にとっては同じ「道具」ではあっても、人間にとってはそうではないのだ。
しかし私たちはそれに気がつかず、当たり前のように「知」にまつわる道具を開発し、生活の中へと浸透させていった。混乱はすでに生じ始めている。
断片化される私たち
ソフトウェアは、データを扱う。そして、データは固定的であり断片的である。量子的な振る舞いが可能な「ファイル」というものが存在しないかぎりは、そうであり続けるだろう。
そのようなソフトウェアが、今では「私たち」を扱っている。
人間、一人ひとりは、本来、創造性の源として取り扱うべきものだ。であるにもかかわらず、商業敵に集団化や抽象化を進めるサイトは創造性の断片を匿名化して提示し、その出典を不明瞭にしてしまう。
Wikipediaのページを、誰が編集しているのかは問題にされない。「十分な量」の人間がそこに関わっていれば、そのページの健全性は高いと判断される。乱暴に言えば、誰だって構わないのだ。
何か情報を探してGoogleを検索したときに、一番上に表示されるページを誰が書いているのかは気にされない。その判断はGoogleが自らのアルゴリズムできちんと行ってくれる。しかもそのアルゴリズムは、他のページからのリンクの多さで決定される。集合知の別の使い方だ。
だから、私たちは安心してその情報を摂取すればいい。今日1.1について調べた記事と、次の日1.2について調べた記事がまったく違う人によって書かれていても、私たちはそれをまったく気にしない。だって、Googleがその記事を保証してくれているのだから。
その感覚は、綺麗に書き手としての感覚に逆流してくる。どれだけ発信しても、「私」は他者にとって何者にもなりえない。ページに付属するAuthor情報の一部でしかない。
結局これはなんだろうか。一番近いのは、分業による労働(およびそれに付随する達成感)の疎外だろう。現代では、人間にまつわる要素がすべて断片化され、結果として、私から「私」が疎外されようとしている。それも、強烈なスピードで。
本書の言葉を借りれば、サイバネティックス全体主義においては、私たちは「誰か」である必要はない。むしろ、そうあるのは邪魔なので、ソフトウェアが粉砕器にかけ、ゴリゴリと削り落とし、フィルターで濾してしまう。
そのつけは、どこかで一気に支払うことなるのかもしれない。
さいごに
本書の射程はひどく広い。目次は以下の通り。
- 第1部 人とは何か
- 第2部 お金はどうなるのか?
- 第3部 フラットの耐えられない薄さ
- 第4部 ビットを最大限に活用する
- 第5部 未来の体液
ここに14の章が含まれる。
もちろん著者は「デジタルツールを捨てよう」みたいな化石しつつある提言を行っているわけではない。むしろ、現代のデジタルツールの在り方は化石的ではないかと主張している。そして、おそらくその通りだろう。
人間の創造性を無価値に(あるいは、そうであるかのように)貶めるものではなく、むしろそれを肯定し、増幅するようなものが登場するのが望ましいとは思う。が、それは難しいのかもしれないと、昨今の状況を鑑みながら考えている。