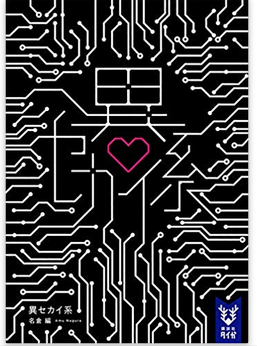たしかにこの作品のタイトルは「異セカイ系」だろうし、それ以外ありえないだろう。
セカイ系であり、異世界転生ものであり、そしてそのどちらでもない。つまりは新しい何かである。
正直、東浩紀さんが「キャラクターをめぐる小説は愛をめぐる哲学の試みである。」と書き、大森望さんが「セカイ系をなろう系に改装し、新本格と重ね合わせる最強のワイドスクリーン・メタフィクション!」と評している時点で、ほとんど言うことはない。見事にこの作品をあらわしている。
でもまあ、ちょっとばかり私も何か書いてみよう。
とりあえず、こてこての関西弁である。正直、第58回メフィスト賞受賞作ということを知らなければ、最初の方で止めていたかもしれない。別段読みにくいわけではないが、あえて感は強い。むろん、これはこれでキャラ立ちのためであり、最終段階に向けての差異のつけ方なのであろう。
で、本作は非常にメタである。徹底的に、圧倒的にメタである。しかも、そのメタの両端をグイーんと伸ばして、片方をひっくり返してテープでくっつけたみたいになっている。メビウスの環的循環構造。そして、そこからセカイを眺める、という趣だ。
全体を通して、ハイコンテキストであり、現代だからこそ書かれ、また受け入れられた作品であろう。その界隈に突き刺さる反面、まっさらでこの本を読んでも、そこまでの刺殺感はないかもしれない。とは言え、チャレンジに満ち溢れた作品であることは間違いない。
途中、『Re:CREATORS』を彷彿とさせるような創作論が展開されるのかと思いきや、その実、この世界の実存にチャレンジする内容なのである。セカイ系を一ひねりすることで、世界へと迫っていく。その手つきは見事というほかない。
もう一度言うが、本作は創作論ではない。創作論を通過して、その先に突き進んでいく。あるいは、生きることは創作なのである、世界が私を作り、私が世界を作る、という意味であれば、創作論といってもいいだろう。どちらにせよ、その二つに大差はない。
神がいて→私がいて→キャラクターがいる。この矢印が、ぐるっと回って循環し始めるとき、この世界を眺める私たちの視点は変容し始める。そういう体験を提供してくれるのが本作である。