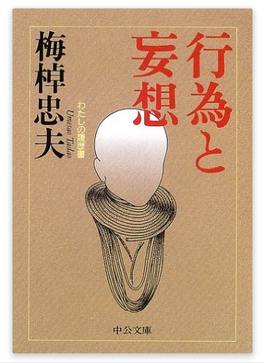梅棹忠夫さんの自伝。京都の幼少期からはじまり、戦中・戦後の青年期を通り抜けながら、初代館長を勤めた国立民族博物館を退官した後までの、70数年の半生が綴られている。
ともかくすごい人だ。そして、非常につかみどころがない。
自身の意欲的な活動は言うまでもない。数多くの文章を提出されているし、さまざまな組織の設立・運営にも助力されている。また、著作集の出版が始まったのが、失明されてからというのがほとんど信じがたい。耳で聞きながらも校正はたいへんだったに違いない。あまたが下がる。もちろん、手助けしてくれる人に恵まれていたから、という環境的幸運はあっただろうが、その幸運を引き寄せたのはまぎれもなく梅棹さん自身の活動だろう。
自分でも書いているように、彼はアジテーターであった。が、単にアジっていた(扇動していた)だけではない。場を与え、チャンスを与えていた。梅棹サロンはその好例だろう。彼は研究会やグループを作り、雑誌を作った。人はそこに文章を載せた。人が集まり、人がつながり、人が知られていった。メディアの力がそこにははっきりと働いていた。
つかみどころのなさはその辺に起因するのかもしれない。梅棹さんはアカデミックな人であったが、ジャーナリズムにも足を踏み入れていた。とても売れた本を書き、そうでもない本も書いている。理系でもあり、文系でもあった。日本で活動しながら、世界も渡り歩いた。日本語を使いながら、ローマ字の運動にも参画した。
なんというか、どのようなテンプレートにも当てはまらない人だ。安易なステレオタイプを徹底的に拒絶するような生き方がここにはある。それにあこがれを感じるかどうかは、もちろん読み手次第だろう。
私が読んでいて、驚いた名前が二つある。一つは、レヴィ・ストロース。私が「こいつはすげー」と思う学者の一人で、よくよく考えてみれば二人の関心領域は重なっているし、12歳ほどしか違わないわけだから面識があったとしてもおかしくはない。が、この二人につながりがあるのが、なんとなく嬉しく感じた。
もう一つは、関西文化学術研究都市。この計画に梅棹さんが関与していたことを知ってかなりびっくりした。が、関西で活動されていたわけだから、そういうことはあってもおかしくない。憶測でしかないが、この計画があったからこそ、関西にも国会図書館が生まれたのだろう。京都の片田舎に住んでいる私ではあるが、国会図書館関西館が近場にあるのは少し誇らしいし、単純に便利である。
というわけで、思想的なものではなく、活動的な部分で梅棹さんと自分とのつながりが感じられた一冊だった。ほくほくした気分である。