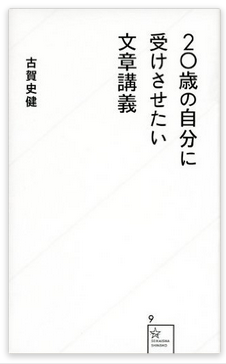文章の書き方というよりも、文章の書き方についての考え方を紹介した本です。
章立ては以下の通り。
・ガイダンス その気持ちを「翻訳」しよう
・第1講 文章は「リズム」で決まる
・第2講 構成は「眼」で考える
・第3講 読者の「椅子」に座る
・第4講 原稿に「ハサミ」を入れる
内容についてある程度予測できつつも、中身が気になる見出しの付け方ですね。参考になります。
ガイダンスにも書かれていますが、義務教育で「文章の書き方」を教えてもらうことはありません。少なくとも私は教えてもらった経験がありません。文法についても、体系的に学んだ記憶はなく、なんとなく「作文」を繰り返していたようなイメージだけです。これだけでスラスラ文章が書けるようにはならないでしょう。
最近の日本では、ブログやSNSによって書き言葉を使う機会が増えていますが、それでも「文章を書くのは苦手だな〜」と感じている人は多いのではないでしょうか。それは、「書くこと」についてあまり学べてこなかったことに理由があるのかもしれません。
著者は、「書くことは、考えることである」と書いています。まさにその通りです。書きながら考える、考えながら書く。表現を変えれば、書くという行為を通すことで「考える」を実践できる、と言えるかもしれません。
もちろん「黙考」も考える行為の一つです。しかし、実際やってみればわかりますが、文章として書いているうちに考えというのはどんどん進んでいくものです。ときに進みすぎて、自分がまったく想像もしなかった場所に着地することもあります。その意外感が、私にはたまらなく心地よく感じられます。だから書くことを止めることはできません。
それはさておき、本書で提示されている「書き方」についての考え方は、それほど奇抜なものではありません。作文技術でよく言及されているものも多くあります。もちろん、それは有用さの裏付けでもあります。
面白いのは、文章を書くことに「翻訳」という概念を持ち込んでいる点です。
頭のなかの「ぐるぐる」を、伝わる言葉に”翻訳”したものが文章なのである。
文章系のアドバイスの一つに、「思った通りに書きなさい」がありますが、実際それを実行するのは難しいものです。
頭の中に浮かんでくるものは、直線的でもなく、言語的ですらない場合があります。それをそのまま紙の上に言葉として書き写すことはできません。仮にできたとしても、他の人が理解できるものにはならないでしょう。
左から右に移し替えるのではなく、頭の中の≪ぐるぐる≫を、他の人がわかる形に「翻訳」すること。これが文章を書くことだと著者は主張しています。今まで文章を書くことを「頭の中のぐるぐるをそのまま出すこと」だと考えていた人にとっては、新鮮な響きがするかもしれません。視点を動かすための表現としては、なかなか上手なものだと思います。
もう一点、共感できるのが、
文体とはリズムである。
です。
このリズムとは、読んだ人が文章から感じる音楽的な感触、ということです。
音符一つではリズムは刻めないように、文章のリズムも一文だけでは見えてきません。文と文のつながり、パラグラフの長さ、句読点の打ち方、漢字とひらがなの割合、形容詞句のバランス、といったものの総合から立ち上がってくるものです。
たとえば、
音符一つではリズムは刻めません。それと同じように文章のリズムも一文だけは見えません。文と文のつながりや、パラグラフの長さ、そして、句読点の打ち方や、漢字とひらがなの割合といったものが合わさってリズムができあがります。ある意味で文章の総合的な体験と言えるでしょう。
という文章が示す意味は、一つ上の文章と同じですが、読んだときに感じる「感触」は違うでしょう。もっと文章をぶつ切りにすることもできますし、逆に長い文章にすることも可能です。
「音符一つではリズムは刻めません」を「たった一つの音符ではリズムは作れません」と表現を変えることもできます。こう考えると、一つの意味を表現する文章のあり方は非常に多様です。
で、そのどれを選択するか、言い換えれば、どの書き方が(著者にとって)「読みやすく感じられるか」が文体として表れてきます。つまり、ある部分まではセンス(感覚)の問題です。
C→Bm→D→F
というコード展開が耳に心地よく響くのか、
C→G→F→Dm
というコード展開に安定感を感じるのかは、人によってさまざまです。
もちろん、破綻したコード展開があるように、破綻した日本語の使い方もあります。「てにをは」が(※)きちんと使わないと、思った通りに意味が伝わりませんし、い、ち、も、じ、ご、と、に、く、て、ん、を、う、つ、の、は、独特ではあるものの「読みやすい」と万人に胸を誇れるものでもありません。
※一応書いておきますが、意図的なタイポです。
最低限のルールとして、文章の決まりごとはあるものの、句読点の打ち方や、漢字の使い方、語彙や表現方法については、何度も読み返して、一番良いと思えるところまで持っていくしかありません。そういう終わりなき修正(実際は終わりがないと困りますが)の果てに出てくる文章が持っているものがその人の文体と言えるのではないか、とそんな気がします。