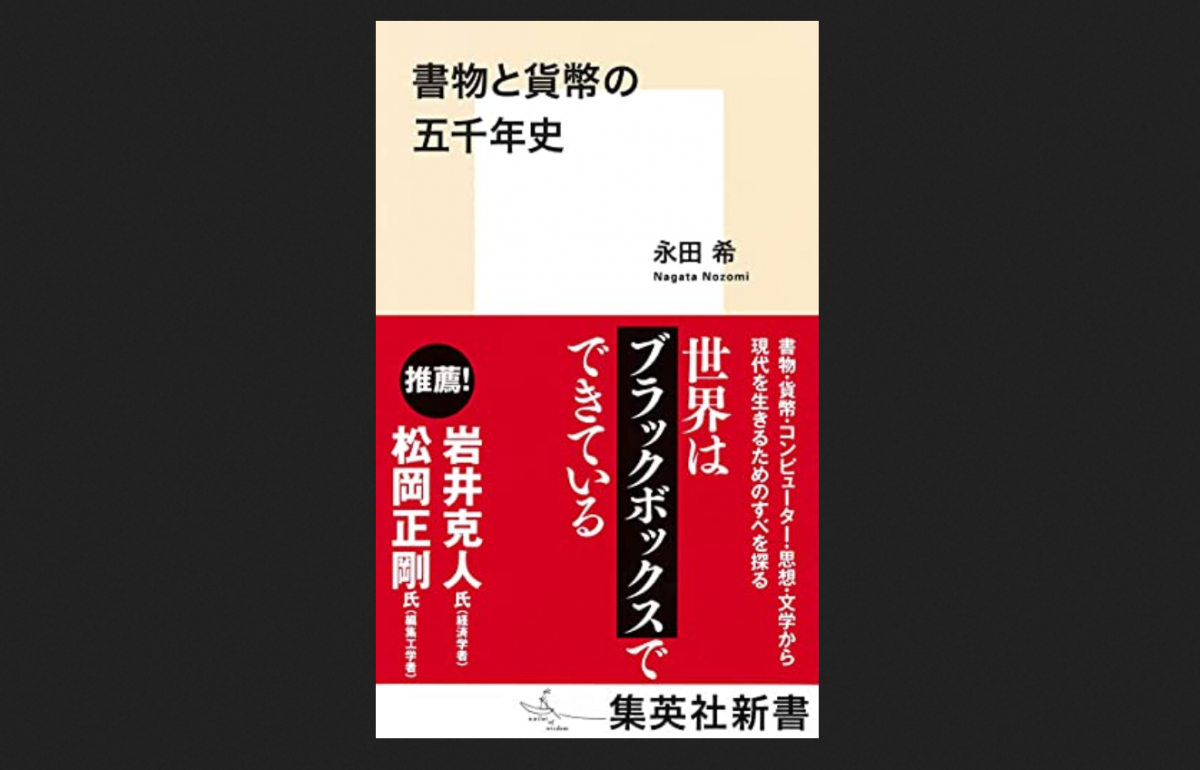本書は、テクノロジー論であり、ブラックボックス論でもある。
と、言い切ってみるのはスタートの勢いを生み出すのにはよいのだが、それで本書をうまく指し示せているのかというと少々心もとない。本書を貫くテーマは概ねそれでよいとして、さまざまな枝葉が本書からは伸びていて、そういうまとめを拒絶するようなところがある。つまり本書もまた、ただしく「ブラックボックス」であろうとしている。
章立ては以下の通り。
第1章 すべてがブラックボックスになる
1.モバイル革命とはなにか
2.スクショとデジタルトランスフォーメーション
3.インターネット革命が生み出したブラックボックス
4.管理通貨制度と電子取引が不可視化したもの第2章 情報革命の諸段階、情報濁流の生成過程
1.情報革命の諸段階、情報濁流の生成過程
2.ルネッサンスと印刷革命
3.中世以前の書物と貨幣
4.文字・言葉・数第3章 人間は印字されたページの束である
1.印象と心像
2.現代思想はブラックボックスをどう扱ってきたか
3.価値とシミュラークル
4.ブルシットジョブと『生きた貨幣』第4章 物語と時間
1.文学作品に畳み込まれた「生きた時間」
2.あなたの人生の物語
3.はてしない物語
4.「話」らしい話のない未来
正方形の箱が並んでいるかのように整った目次である。流れはこうだ。
まず前半の二章で歴史を遡る。最新のコンピュータからはじまり、文字文化の誕生へと時代を遡行していく。私たちはそこで、あるテクノロジーが、別のテクノロジーの上に成立していることを確認することになる。技術は重なり合い、系譜を綴っていく。その確認が準備運動である。
続く後半の二章では、その理解を踏まえた上で、より踏み込んだブラックボックス論が展開される。前半が技術に関する話に注力していたのに対し、後半二章は思想・文学の話へと傾く。この段階でずいぶんフィールドが広い本だということがわかるだろう。あまりにも広すぎて、先が見通せないくらいである。言うまでもなく、それが本書の魅力だ。ものすごく整った目次/構成でありながら、その中身はさまざまに枝を伸ばしている。だからこそ、本書を一言で言い表すのは難しいのだ。
しかし、そうはいっても本書において「ブラックボックス」が重要なキーワードであることは間違いない。
中をあけてみないと、どうなっているのかが外側からはわからない箱。
それが「ブラックボックス」である。これは実に興味深い話だ。
たとえば私はテレビのリモコンを操作することで、遠隔のテレビを操作している。そこでは赤外線が何らかの働きをしていることは予想できるが、それ以上のメカニズムはまったくわからない。にも関わらず、私はリモコンが使えている。私から見て、リモコンを成立させているあらゆるテクノロジーが「ブラックボックス」なのだ。
スティーブン・スローマンとフィリップ・ファーンバックによる『知ってるつもり――無知の科学』では、そのような状態を「認知的分業」と呼んだ。そのことを知っている人がいて、その人が自分の技術を作ってプロダクトを作るからこそ、私たちはその技術を直接知らなくてもそれを「使う」ことができる。間違いなく、人類がここまでの文明を築けたのは、そうした認知的分業が可能だったおかげであろう。まさしく、私たちの世界は「ブラックボックス」によって成立している。
一方で、本来そうした技術は「目に見えない」ものであるし、それが目指される。マーク・ワイザーが提唱した”Calm Technology”という概念はまさしくそれを体現するものであろう。だとしたら、私たちはそれがそこにあることすら気がつけないことになる。ブラックボックスはたしかに不透明ではあるが、「不可視のものがそこにある」という可視化は為されているわけだ。
本書はまさにそういう仕事をしている。「ここにブラックボックスがあるよ、あそこにもブラックボックスがあるよ」と指さして回っているわけだ。私たちはそれを聞いて、「なるほど、たしかにここにはブラックボックスがある」と認識できる。そして、一度でも認識したら、その中身が気になってくる。リバースエンジニアリングが始まるのだ。
逆に言えば、リバースエンジニアリングが駆動するのは、そこに「ブラックボックスがある」と認識できたときである。そうした認識がない状態は、完全な透明になっており、「中身」に注意を向けることもない。この点が重要だろう。
その意味で、教養とは「世界がブラックボックスでできている」という認識を持っている状態を指すのかもしれない。仕組みをすべて理解しているのではなく、自分が理解していない仕組みによってこの世界は成り立っているのだと直覚している、ということだ。基本的に、読書の沼に嵌まり込むのは、そうした認識を得てからである。なにせブラックボックスは入れ子状に構成されており、基本的に際限というものがない。どこまでも中身の探究は続いていく。逆に言うと、その探究があっさり終わってしまうものは、ブラックボックスを無視していると言えるだろう(私が知る陰謀論はたいてい箱を一つ空けて終わりになっている)。
ともあれ、私たちは完全に透明になっているもの(ブラックボックスだと名指されてすらいない状態)については、適切に価値を見定めることができない。世界はただ「そうなっている」ように思えるからだ。テクノロジーが入れ子状に高度なればなるほど、私たちはその価値を計れなくなる。この点が、現代社会の避けがたい課題であろう。「すべてのブラックボックスをきちんと知りましょう」という啓蒙に無理がある以上(そんなことは誰にも不可能だ)、何かしらのひねりが必要となってくる。少なくとも、「もっと勉強しなさい」といった安直なセリフでは何も解決しないのである。狼少年のような、ブラックボックス老人が今こそ必要なのかもしれない。
* * *
さて、本書の最後で語られている「生きた時間」が少し心にひっかかった。
私たちには、たしかに生きている時間(クオリアを感じるその瞬間)があり、それが何かしらのメディアに「記録」された時間がある(そのメディアは脳であってもよい)。生きている時間はいわばむき出しの生であり、マインドフルネスなどでフィーチャーされるような「今=すべて」のような感覚でもあるだろう。
私が思うに、人が生きるとは、そうした「生きている時間」と「そうでない時間」の折り重なり(ないしは綱引き)にあるのではないか。言い換えれば、人の人生もまた、本と同様に閉じと開きが重なるところにあるのではないか、ということだ。
「今=すべて」の感覚は、ある意味で「すべてがわかっている状態」である。それはつまり、ブラックボックスが何もない状態だ。しかし、人間にとって、自分自身ですら本来はブラックボックスである。今さらフロイトを持ち出すまでもないだろう。私にとって、十全にわかる「わたし」とそうでない「わたし」が重なるとき、私の目は開かれ、世界にブラックボックス的まなざしを注ぐのではないか。
内部へのまざなしと外部へのまなざしは呼応している。
だから、外部のブラックボックスから入っても、内部のブラックボックスから入っても、結局は同じ場所にたどり着くのだろう。すべては、入れ子状のブラックボックスでつながっているのである。