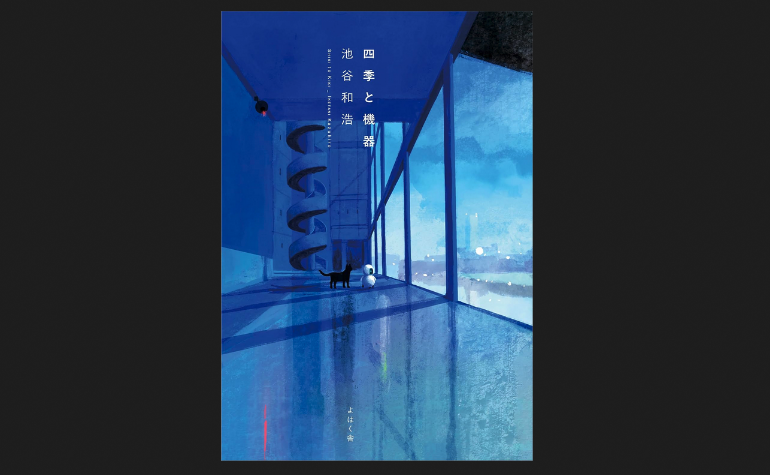おそらく冒頭は読みづらいだろう。カメラがどこにあるのかがわからないのだ。
つまり、一般的に小説というものには視点があり、一人称ならその人物の目線、三人称ならそれぞれの登場人物の近くある仮想のカメラがそれを担っている。語り手がどこから何を観ているのか(あるいは観ることができるのか)を規定するもの。
だから一人称視点なのに、目の前の相手の心の声が語られるのは──当人がエスパーあるいは相手がサトラレでない限りは──タブーとなる。そんな風にカメラは小説を規定する装置である。
もちろん、本当に小説の中にカメラがあるわけではない。これはメタファーだ。カメラというテクロジーをベースにしたメタファー。それが小説の書き方を規定している。
では、別のテクノロジーをベースにしたメタファーは可能だろうか。もっと違う想像力によって場面が描かれる小説は。
たとえば一台のカメラが人間に追従するのではなく、複数のカメラが同時並行的に起動していて、それを一枚の画面で観ることができるというテクノロジーでは? 警備室で複数の防犯モニターを眺める人のように。
その人の視点では、さまざまな場所で同時並行的に物事が進んでいく。カメラは単一ではなく遍在/偏在しており、ただ視点を移せば別の場面が目に入る。
そのようなテクノロジーをベースにした場面の描き方は可能だろうか。そう、本作品のように。
世界の生成のスタイル
私たちは小説を「読める」ようになると、そこでどんなことが行われているのかを意識しなくなる。小説を書く方もその「読まれ方」に合わせて書くので、何もかもがなめらかに流れていく。
そこで行われている生成──ある種のプロトコルに沿って世界が生成されること──が、ただ情報のインプットであるように感じられてしまう。
実際はそうではない。私たちは小説を読み、そのプロトコルに合わせて毎回世界を生成している。そして、そのプロトコルそのものも生成されうる。
本書にはたくさんの()が出てくる。最初の方は登場人物の内的な語りが()を用いて表現されているのだろうと思った。文章ではよくあるプロトコルである。
最初の方はその認識で破綻はない。何か意味深に感じられるものもあるが、小説なのだからそういうこともあるだろうというプロトコルで片づけられる。しかし、p.26の以下の部分は無理だった。
指に大きなリングをいくつも嵌めていた。いつものネックレスと同じブランドの、陰影の濃いシルバーリングのアクセサリだが、そのブランドがなんという名前だったのか灯子はそれが思い出せなかった。(クロムハーツだ。)
これが内的な語りでないことは間違いない。だって「思い出せない」と語られているのだから。一方で、これはたしかに誰かの内的な語りである。
それに気がついた瞬間、私のシークバーが本作の冒頭までギュンと戻った。カメラが再設定され、世界の生成そのものがリスタートしていった。なんともビックリな体験である。
本作は作品の内部にさまざまなテクノロジーが出てくる。デジタル・テクノロジーに意欲的な架空の大学が舞台で、四つの章(2018、2019、2020、2021)はおそらく同じ日付を扱っている。年が一つ進むたびにテクロジーが進歩していく様子は、SF作品と同じような楽しみ方ができるだろう。
しかし、本作の意欲はデジタル・テクノロジーが当たり前に使われるようになった世界を描くことだけに向けられているわけではない。むしろ、そうした世界で人々はどう世界を「感受」するのかを描こうとしている。言い換えれば、当たり前のように使われるテクロジーは、私たちの世界の知覚のスタイルそのものを変えてしまうだろう、という著者の世界観が基底にある。小説の語り方もまた、そのスタイルと共に変化していくのだ、と。
作家というのは基本的に新しいものを作っていく存在だが、著者はたしかに新しいことを描こうとしている。それもかなりラディカルなことを。