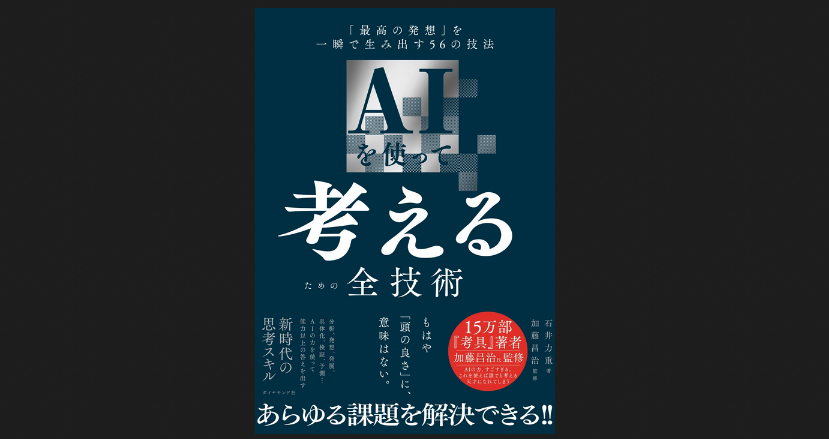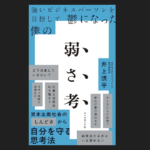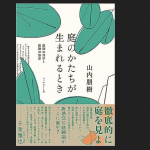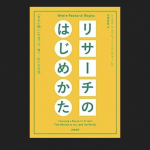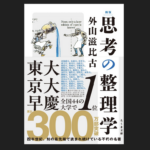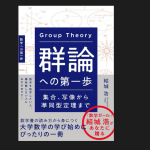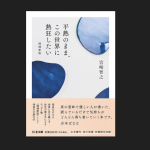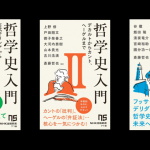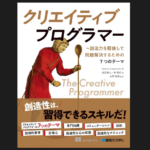前々から感じていたことだが、考えることが得意な人は生成AIを使うのも得意である。それはまあそうだろう。考えるという行為のコアは、問いの技術であり、問いの技術はそのままプロンプトの書き方につながっている。
考えるということをするとき、人は自らで問いを立て、その問いに答えようとする形で思考を進めていく。立てられる問いによって、その後進んでいく思考プロセスの姿は変わる。どのように問うかが、答えの形を先駆的に定義するとすら言えるかもしれない。
いわゆる「発想法」と呼ばれる技法は、状況に合わせて適切に機能するように調整された問いである。道具としての疑問。この道具のバリエーションが豊富なほど、いろいろな物事を、いろいろな面で検討することができる。アイデアもまた、そのような多面的な検討から生まれてくる。
本書はそうした発想技法を、人間の脳にインストールして使うのではなく、むしろ生成AIへのプロンプトとして利用することを提示する。とは言え、それは「AIに考えさせる」ためではない。本書のタイトルにあるように「AIを使って考える」ためである。
目次は以下の通り。
- はじめに ──「AIを使って考える時代」がやってきた
- 序章 「AIを使って考える」とは? │ チュートリアル
- 1部 すぐにアイデアがほしいとき
- 第1章 「AI特有の力」で考える
- 第2章 「自由な発想」で考える
- 第3章 「ロジカルな発想」で考える
- 2部 アイデアを磨きたいとき
- 第4章 考えを「発展」させる
- 第5章 考えを「具体的」にする
- 第6章 考えを「検証」する
- 3部 アイデアを実現したいとき
- 第7章 アイデアの「伝え方」を考える
- 第8章 アイデアの「実行策」を考える
- 4部 考えるヒントがほしいとき
- 第9章 「課題」を分析してヒントを得る
- 第10章 「悩み」を分析してヒントを得る
- 第11章 「人」を分析してヒントを得る
- 第12章 「未来」を予測してヒントを得る
- 最終章 「技法」を使いこなす │ ケーススタディ
もう一度、人間の脳が「考える」状況をイメージしよう。何か考えたいことがあったとして、それに対して問いを立て、その答えを自分で考え、その考えに対してまた別の角度からの問いを立て、さらにその問いに答えを出す。主語となるものは「自分」しか存在しないが、知的な活動の内実を見つめてみると、そこには複数的な存在が感じられる。Aの角度から質問する存在、Bの角度から疑問を提示する存在、Cの角度から……。さまざまな「自分」が共同的に取り組んでいる。
私たちは、ひとりで考えているときですら、「一人」ではない。多様な検討が行われていたら、必ずそこに複数的な存在が立ち上がっている。
だったら、そのメンバーにAIを加えたって何も問題はない。むしろ非常に強力なパートナーとなってくれる。
たとえば技法5「各種専門家の案」では、以下のようなプロンプトが提示される。
多数の専門家(クリエイティブな専門家、技術専門家、ビジネス専門家、学術研究者、社会科学者、ユーザー、ディスラプター、ユーモアのセンスを持つ人々、冒険家として〈アイデアを得たい対象を記入〉について具体的な案を考えてください。
自分ひとりでもさまざまな切り口を出すことは可能だが、ここまでバリエーションを拡げるのは難しいだろう。また、チームなどで普段ブレストをしていると、どうしても偏り方が偏ってしまうので、上記のようにAI専門家を召喚するのは良い刺激になる。
私なんかも、哲学の小難しい議論をするとき、身の回りにそういう話ができる人間がまったくいないので、深掘りすることも新しい風を入れることも難しいのだが、ChatGPTならば簡単に議論に応答してくれる。普段接することのない、「高度な知識」との接触を可能にしてくれる。
もちろん、それらは「答え」を提示してくれるものではない。そうではなく、自分の考えを新しい角度から検討するための視点を提供してくれるのだ。この価値は、相当に大きいだろうと推測する。
付言すれば、もし「答え」を得るためではなく「もっとよく考える」ために発想技法を練り込んだプロンプトを使っていれば、徐々にその発想技法が当人の脳にもインストールされていくだろう。人は真似て学ぶ存在なのだ。
今後数年で、知的な作業をするときに生成AIを使うことは、長い文章を入力するときにタイピングするのと同じくらい当たり前になってくるだろう。そういう時代だからこそ、「よく考えるための技法」に通じていることには意義があるように思う。