もし、今「仕事」や「働くこと」に迷いを感じているならば手にとってもらいたい一冊。
『自分の仕事をつくる』の続編で、やはりテイストは、掴まえにくいもの、語りにくいものを、やわらかく、でも実直に扱っている。その慎重な手つきは、そこに大切なものがあるのだろう、と予感させる。メディアはメッセージなのだ。
固く、断定的に語ってしまえば、壊れてしまう何かはたしかにある。そして、生きることに関する多くの物事が、そのようなものなのである。離散的で、動的で、矛盾をはらみながらも、一つの方向を目指そうとする意志を持つ。なかなか扱いが難しい。
では、本書のタイトルでもある「自分をいかして生きる」とは何を意味するのだろうか。
■
戦後の高度経済成長を経て、我々は豊かになった。きっとたくさんの人たちが、がむしゃらに働いてきた蓄積がそれを支えてきたのだろう。
豊かさは、現代を生きる我々に働くことに関する自由を与えてくれた。家督を継ぐことは絶対ではなくなったし、出生地によって仕事が限定されることもなくなった。教育の普及は、職業選択の自由(実際にそれを選べるようになること)にも貢献する。基本的に、それはすばらしいことだと思う。
しかし、働くことに関する自由の出現は、同時に働くことについての悩みも生み出した。自由は、責任を伴う。世の常である。
働くことを、自分の人生にどのように位置づけるかは、人それぞれだ。そこに正解はない。だからこそ、選ぶのが難しい。ジャム実験もそれを支持している。
その悩みにつけ込んでくる輩も絶えない。「正解」がないところに、仮初めの正解を持ち出すのが彼らの仕事だが、とは言え、「あなたの人生は、実はこうなんですよ」と言ってもらえれば、選択の悩みからは解放される。でもそれは、選択の自由をみせかけだけは保持したまま手放すことと同じである。
こういう言い方はあれだが、古代ギリシャの奴隷は、「働くとは何か?」「自分らしい生き方とは?」などと悩むことは(あるいはその暇は)なかっただろう。悩むこと、ひいてはそれについて考えることは、常に選択の自由とセットになって訪れる。悩むことを避けるために、考えることを捨ててしまうのは、本当に懸命なことだろうか。
■
著者は、「考えること」を大切にしている。また、読者にそれを促そうともしている。だからこそ、本書には「かくあるべし」という生き方論は登場しない。さまざまな人の「生き方」「働き方」をたずね、そこに著者なりの考察を織り込んでいく。そこには、選択の自由の重要性が、あるいはその結果を自分で「引き受ける」ことの大切さがにじみ出ている。
かといって、過剰なまでの「自由で、なんでもいいんだ」という破壊的な、あるいはアナーキーなスタイルが顔を出すことはない。
どうしたって、人が生きて語る(≒生きた人間が語る)という時点で、そこには価値観や世界観が埋め込まれる。根本的な部分においては、本書は「何でもいい」と言っているわけではない。人の心の内側にあるであろう、ある種の方向性を(あるいはそれを認めることを)是としている。
「労働は美徳」という考え方は、いかにも専制的ではあるが、かといって、私たちの心にある「いいこと」をしたいという欲求は、文化や制度から植え付けられたものに過ぎないと断じられるだろうか。たとえそれがゲームでも、やっぱり私たちは「いいプレイ」をしたいと思う。そして、それを達成すると、充実感が心に染み渡る。その感覚を大切にして、〈自分の仕事〉について考えることは、意義のあることなのだ、という著者なりの思いが本書の軸であろう。
「自由で、なんでもいいんだ」であれば、心を空っぽにし、感情を押し殺して、奴隷のように働かされることもまた「よいこと」になってしまう。それは違うだろう、と著者は感じているわけだ。
■
働くことや生きることに関する重要な点は、それが他者に対して開かれている、ということだ。あるいは社会に対してと言い換えてもいい。
そもそもとして、「自分」というものですらそうなのだ。我々は、完全に独立した自我を有しているわけではない。自我の形成や維持には、社会的な関係が、言い換えれば他者が与えてくれる情報が影響している。そのことをすっかり忘れて、「自分らしく生きる」とか「好きなことを仕事にする」というと、途端に現実感がなくなる。自分に閉じた仕事は、仕事とは呼べない。
仕事は、個人が社会とコミットする一つのメディアであるし、それをどう利用するかは、長い人生において重要であろう。森に籠もって生活していても、その森が住宅地開発のために伐採されるとなれば、いやがおうでも社会と関係性を持たなければいけない。
一つだけ言えることは、戦後の日本社会が形成してきた「仕事観」は、唯一絶対のものではなく、むしろある社会環境に最適化された、それも過剰に最適化されたもの(日本文化が得意なことだ)に過ぎない、という点だ。それを出発地点にして、かつ馬鹿馬鹿しいアナーキズムにはまりこむことなく、しっかりと「自分」のいかし方を考えていきたいものである。
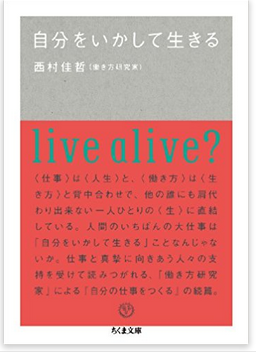









One thought on “『自分をいかして生きる』(西村佳哲)”