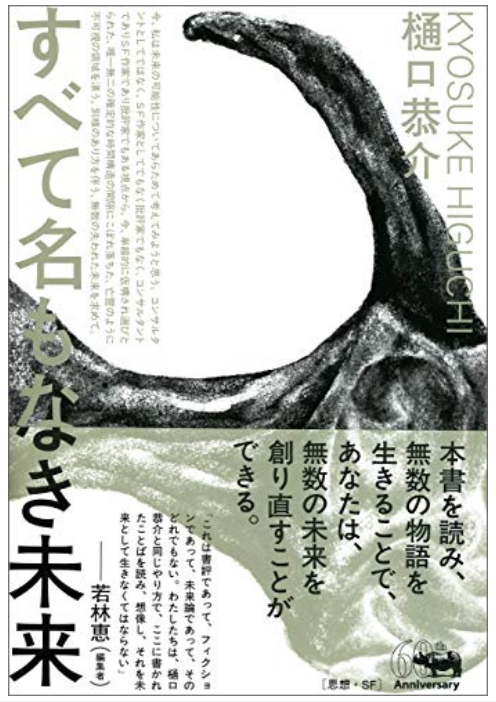はたして本書は書評集と言えるのだろうか。私にはそれがわからない。
なぜわからないかと言えば、私は書評集をほとんど読まないからだ。一番最近に読了した書評集と言えば、スタニスワフ・レムの『完全な真空』であり、この本は存在しない本についての書評集というおどけた(あるいはボルヘス的な)調子で書かれているので、一般的な書評集とは位置づけが異なるだろう。だいたいにして、書評集を読むくらいなら、その時間で実際の本を読んだほうがよいなどと考えている不逞な輩なので、書評集の一般的通念など持ち合わせがない。むしろ、『バーナード嬢曰く。』のように面白おかしく本を紹介してくれたほうがテンションがあがるくらいである。
だから私は本書が書評集と呼べるかどうかがわからない。それを判断するための物差しを持ち合わせていない。
その上で、あくまで印象として述べるならば、本書は書評集であって、書評集ではない。むしろ、本をカタリストとして著者の語りをこの世に顕現させているような、そんな感触がする。もちろん、これはあくまで私の読みであって、あなたの読みと重なるわけではない。ある人はこの本を書評集と読むかもしれないし、別の人はフィクションと読むかもしれない。本の読み方は開かれている。あくまで、ここに列挙されるのは、私の印象に過ぎない。
では、その(私の印象から見た)著者の語りとは何だろうか。
本書は大きく二つのパートで構成される。Side Aは「未来」であり、SIde Bは「物語」である。そしてこの「未来」と「物語」の関係こそが、本書によって顕現される著者の語りである、と私は感じる。
まず「未来」からいこう。はたして未来は確定しているのであろうか。ラプラスの悪魔は退けられたが、それでも私たちの社会がシミュレート過剰に陥っている点は否めない。収集される個人のデータと、高速でサイクルされる機械学習。メディアがメッセージであり、マッサージであるならば、私たちはまさにそれがシミュレートされたからこそ、その通りに生きようとするシミュレーションの自己成就が起こるかもしれない。
そうでなくても、未来は暗い。神が死に、国家が衰退化し、すべての権利と責任が個人に帰着する中で、その個人はまるでその力を振るえていないばかりか、集団化する中で、ポピュリズムの泥濘におぼれてしまっている。希望に満ちあふれたインターネットの黎明期と、現在のインターネットの惨状を比較すれば、魔法少女一人分くらいの熱力学的エネルギーが取り出せるのではないか(希望から絶望への相転移)。
その悲惨さは、加速主義が一定の指示を集める土壌にもなっているだろう。そして、そこでは世界は確定的なのである。資本主義のエンジンをまっすぐ加熱していけば、いずれオーバーヒートするなり自戒する。そう期待できるのは、道のりがまっすぐだからだ。直線でこそ、アクセルはベタ踏みできる。これ以上、もう何も変化が起きないという絶望(あるいは確信)こそが、加速主義を肯定する。そこでは、未来はもう決まりきっているのだ。
たとえその未来が、超資本主義の絶対的支配下ではなく、もっと穏便なユートピア/ディストピアであっても状況は同じである。すべてが決定されている(あるいは決定不能な)状況に置かれているとき、未来は存在しない。なぜなら、そこでは常に同じ現在が繰り返されるだけだからだ。nと、n + 1による数学的帰納法。その世界では、明日とは今日のコピーである。n日後は今日とは変わらない。そして、今日と変わらない世界を私たちは「未来」と呼んだりはしない。私たちは「今日」に閉じこめられている。それが、未来の喪失ということである。
では「物語」はどうか。
物語は、──特に虚構の物語は──、ズレを生み出す。「この世界」ではない世界を描くこと。それが虚構の仕事であり、その二つの世界の差(x-y)こそがズレである。ズレは、差異をもたらす。物語は、差異をもたらす。
現実は一つしかないが、そこからのズレ方には無数のパターンとバリエーションがある。差異は無限に広がる。いくらでも生み出し続けられる。
さらに、虚構によって生み出された世界自体もまた、ズレの対象となりうる。無限は多重に広がっていく。差異は反響し、残響する。それは、瞬間瞬間に生まれては消えゆき、それが無限に繰り返される(西田哲学の非連続の連続)。
物語は、永続的だからではなく、むしろそれが消えゆくから(そして即座に新しく生まれるから)こそ強力なのだ。それこそが物語と現実の「作用の違い」である。
もし、強力な物語が誰かの脳を支配し、その人がその物語に、その物語だけに捕らわれたとしたら、その物語は、もはやその人にとっての「たった一つの現実」となる。ズレは消えうせ、単一の物語が繰り返される。まるで、n日後の今日のように。
物語は、ズレを持ち、無限の広がりがあり、さらに消えてはまた生まれ来るからこそ、現実に対峙できる。「たった一つの現実」に対抗しうるのは、「たった一つの物語」ではない。それでは単に独裁政権の長を、別の独裁政権の長にすげ替えたにすぎない。多数の、消えゆく、ズレた物語こそが、現実に対峙しうる。物語は、無数の物語でなければならない。
そうであるからこそ、私たちは「たった一つしかないこの現実」を、いくようにも読み替えていくことができる。そして、読み替えた先の世界もまた、読み替えていける。変化の再帰性を維持することができる。
未来が確定的であったにしても、いや、未来が確定的であると思われれば思われるほど、物語の力は重要になってくる。未来を(つまりn日後の今日でない世界を)生み出すために(思弁的に実在させるために)必要なのは、無数の泡のように生まれては消えゆく物語たちなのだ。
物語を語ることは、あらゆる可能性を祝福することである。それが現実的でなくても、いっそ現実的でなければないほど、それは言祝がれるべきなのだ。
言葉を持つ私たちは、「この世界」以外を生きることができる。たとえそれが一時的な対比に過ぎなくても、いっそ「逃げ」と呼ばれたとしても、まるで関係がない。この世界とは別様の世界に触れることは、この世界をより深く知ることであり、この世界をより深く愛することである。
それは世界を美化することとは異なる。この世界は基本的に、絶対的に、網羅的に、秘密的に、緊急的に、切迫的に、情動的に、どうしようもない世界である。そして、それと同時に(あるいはそうであるがゆえに)、この世界はきわめて素晴らしい世界である。その二つを、異なる可能性を内包するその世界を受諾すること。了解すること。それが、物語と、多数の物語と生きることである。
というわけで、私は本書をカタリストにして、私の語りたいことを語ってみた。本書が書評と呼べるかは、読者の皆さんの判断に任せることにしよう。
どちらにせよ、本の読み方は開かれているのだ。この世界の可能性と同じように。