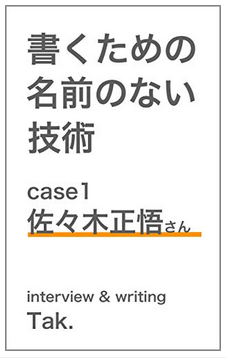本を書くという行為は、ひどくやっかいである。
なにせ私たち人間は、多くのことを真似て学ぶ。見て学び、聞いて学ぶ。しかし、本を書くという行為は、なかなか見ることも聞くこともかなわない。それはまるで、誰も足を踏み入れてはならない最奥の部屋で行われる秘術のようなものだ。真似て学ぶのは不可能に近い。
もちろん、「本を書く行為は学べるのか」という根本的な疑問はあるだろう。私という個別的な現象と、世界という雑多な現象が交じり合う地点に「本」という出来事は生じる。そこに技術が介入できる余地はあるのだろうか、と問うことは可能だ。しかし、どんなところにも、技術はありうる。繰り返される行動において、技術の萌芽はどんな場所にも見出せる。だからきっと、本を書くという行為においても、そうなのだ。
本書は、インタビューという「語り」の中で、そうした技術を見出そうとしている。取るに足らない、別段トピックを立てて語るようなものではない、と当人が思っているような技術の萌芽を見つけ出そうとする。それは少しでも生産性をあげるための工夫かもしれないし、気持ちよく執筆を進めるための環境作りかもしれない。あるいは、もっと全然別の何かということもありえる。
なんにせよ、本を書くという行為は、ひどくやっかないのである。
やろうと思ってハイできました、というわけにはいかない。いつだって苦労はつきまとう。だからこそ、自然と工夫も要求される。そう、執筆活動というのはそういう厄介さとの長期的な関係性でもあるのだ。苦労すればいい本が書けるわけでもないし、苦労しないからといって誰かに褒められるわけでもない。
一冊一冊の本は、毎回「新しく」作られて、そのたびごとに考えることが要求される。しかし、それを為す当人は、あいもかわらず同じ存在なのである。だから、介入する余地はある。でもって、人間という同じ共通項を持つならば、他の人間にだって使える何かは出てくるだろう。それが本のちょっとした技術でしかないにしても、あるとないのとでは大きな違いが生じる。技術というのは、そういうものなのである。
一方で、「自分の方法」を確立している(あるいはしつつある)人間でも、他人の方法を知ることは良い刺激剤となる。むしろ自分と違えば違うほど、その刺激力は高まるかもしれない。目指すものが違い、求めるものが違い、手つきもスタイルもまったく異なっている。でも、だからこそ見えてくるものがある。考えさせられるものがある。
その意味で、技術の話はどちらにしても楽しめる。本書のシリーズが増えれば増えるほど、その楽しみ方もまた増えていくだろう。