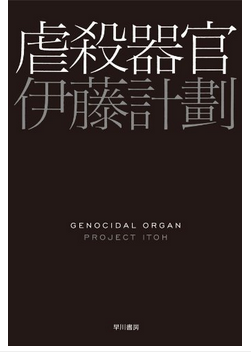もし魂が存在するならば、それこそが唯一この世界のおいてイデアと呼べるものになるだろう。何にも侵されることのない根源的存在。それが思考の主体である限り、思考は言語に先行するはずだ。魂が言葉を紡ぎ出す。言葉は魂を規定しえない。
でも、それは本当だろうか。我々に魂なるものがあるとして、それがアクセス不能とは限らない。もっと単純に、我々は魂などというものを持ち合わせていないのかもしれない。我々とエラー持ちの哲学的ゾンビとは見分けがつかないのかもしれない。そして、そのエラーを地獄と呼ぶのかもしれない。
伊藤計劃の処女作でもある本作は、悲しい作品だ。力のある作品ではある。むしろその力は圧倒的と言っていい。幻想的で、思弁的で、どこまでも暴力的だ。しかし、この作品は悲しい。それは、人が死ぬからでも、戦争が終わらないからでもない。もちろん、作者が早くに逝ってしまったからでもない。この世界の記述の仕方(スタイル)が、どうしようもない哀しみに満ち溢れているのだ。救いはどこにもない。
虐殺王ジョン・ポール(皮肉なネーミングである)は、暴力からもっとも遠い場所に位置しながらも、一番暴力に対して自覚的な存在である。それは言葉のなせる技でもあるのだろう。言葉のない世界には矛盾など存在しえないのだから。
彼のスタイルは、極めて冷静なリアリズムであり、ニヒリズムでもある。私たちは、その世界を直視した上で、それを乗り越えなければならないだろう。もしかしたら、その超克はいつか彼自身の手で示されていたのかもしれない。あるいは、より混迷さを増していた可能性もある。どちらであっても、それは詮無いIfである。
どれだけ滑稽であろうろも、私たちはこれからも物語を紡いでいく。それが、生きる意志ということだ。