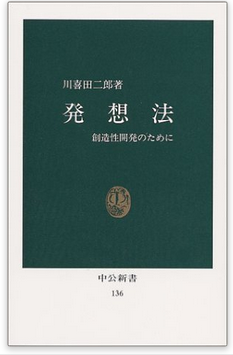おそろしく大きなタイトルだが、普遍的な発想法というよりも、KJ法という発想手法(発想技法)についての解説がメインである。
とは言え、それだけでもない。著者はまず、「野外科学」について説く。この野外科学とは何かと言えば、書斎科学・実験科学と並んで位置づけられる科学のスタイルである。書斎科学は、ようするに安楽椅子科学ということで、書斎に籠もって、思索の中で展開される科学だ。そこでは、古典というものが重要視される。
実験科学は、言葉通り実験と観察を重要視する科学のスタイルで、おそらく人類が「神がすべてを知っている」というパラダイムから決別したときにその大きな歩みが始まったのだろう。現代で科学と言えば、基本的にはこの実験化学が意味される。
では、この実験は何をもたらすのかと言えば、「ほんとうかどうか」を確かめる行為である。思索の中で行われる科学には、それを決定づけるものは存在しない。この違いこそが、実験科学が主流になった理由でもあろう。
さて、ここで野外科学である。野外科学は、その言葉が示すとおり、野外で行われる科学である。つまり、書斎の中でもなく、実験室の中でもない、ということだ。性質としては、経験や観察を重要視する点で実験科学に近いのだが、その実践場所が野外なのである。
この場合の「野外」も「実験室」も、一つのメタファーであって、本当に実験室の中だとか屋外という意味ではない。そうではなく、状況を管理・制御しているかどうかがポイントである。実験化学では、再現性を求めるために、状況は制御され、管理されていなくてはならない。野外科学は、そのような姿勢を持たないわけだ。むしろできるだけ「そのまま」を観察して、何かを取り出そうとする。一回性と対峙すると言い換えてもいいだろう。著者はその「そのまま」を、現場ないしはフィールドと呼ぶ。つまり、野外科学=フィールドサイエンスなのだ。
では、なぜその野外科学において発想法(本書ではKJ法)が役立つのかと言えば、実験科学では立てられた仮説を検証するところが重要視されるのに対し、野外科学ではむしろその仮説をどのようにして立てたらいいのかが重要視されるからだと著者は説く。もちろん、実験科学で仮説を立てることが不要だ、という話ではない。ただ、野外科学では状況とそこからもたらされる情報は、必ず混沌から始まるので、そこから秩序への道筋(つまり何かしらの仮説)を立てないことには話が始まらないことは確かだろう。
そして、この視点をとれば、実は野外科学のフィールドはおそろしく広がることになる。たとえば、ビジネスは野外科学そのものである。ビジネスパーソンが対峙するのは、完璧な法則性に支配された状況ではなく、むしろ混沌とし、一回きりの状況なのである。その中でも、何かしらの仮説を立てて、ビジネスを前に進めていかなければならない。
もっと言えば、私たちが生きることそのものが野外科学だと言える。人生に起こるさまざまなことは、実験室の中の出来事ではない。まるっきりの野外だ。そこで、観察と仮説の力を持って生じる問題に対処していかなければならない。そのように考えれば、野外科学で必要な力は、生きていく力だとも言える。発想法は、サバイバルに必要なアーツなのだ。
そのような視点で本書を読み返してみると、アカデミズムにまるで無縁な人でも得るものが何かしらはあるだろう。
▼目次データ:
Ⅰ 野外科学 現場の科学
Ⅱ 野外科学の方法と条件
Ⅲ 発想をうながすKJ法
Ⅳ 創造体験と自己変革
Ⅴ KJ法の応用とその効果
Ⅵ むすび