『はじめての批評』の増補改定版くらいの位置づけだろうか。タイトルからは若干わかりにくいが、「批評」に焦点が当てられている。といっても、ここでいう「批評」は広い意味を持つ。
表現作品やデザイン、工業製品やサービス、人物や環境など、あらゆるものにはそれぞれに価値が存在します。そうした対象の持つ価値を発見し、文章化する行為が、批評です。
(強調原文ママ)
このような批判にトライすることが、「書くための勇気」と接続すると著者は述べる。なぜか? 冒頭の漫画の一コマがそれを示す。
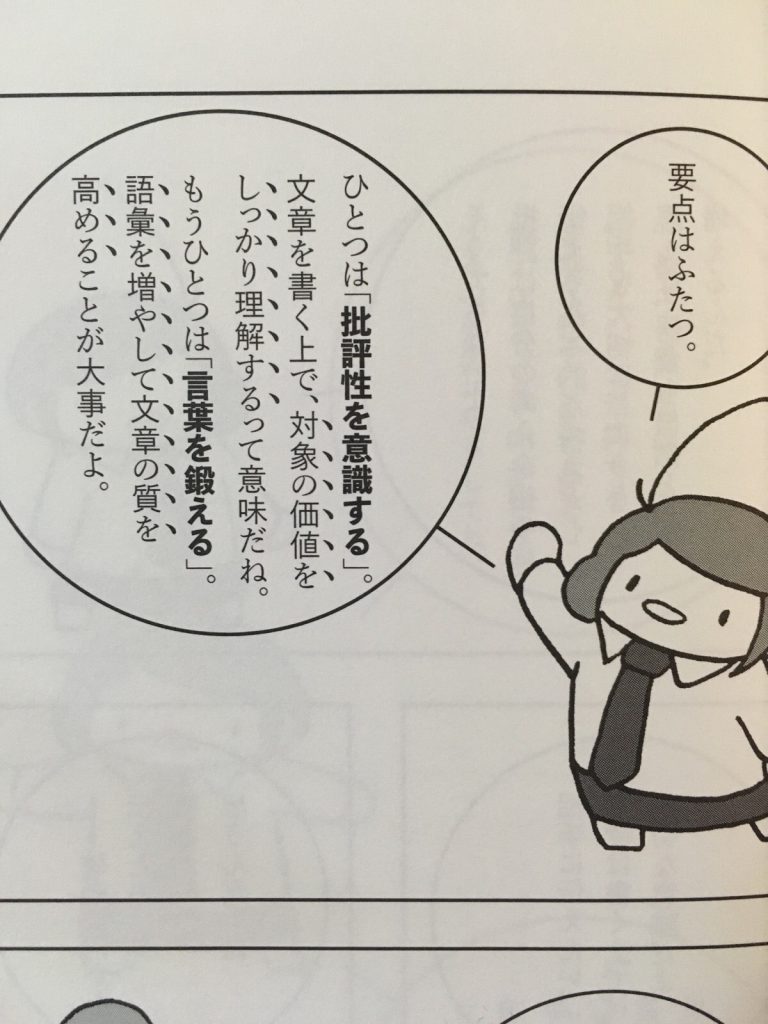
理屈は簡単だ。批評というものが、対象の価値を発見し、それを誰かに伝えるための文章だとするならば、もちろん最初に価値を発見できなければいけない。「おもしろかった」という感想を出発点として、「どんな要素が私に面白さを感じさせたのだろうか」という問いを経由し、「では、類似の要素を持つ別の作品と比べればどうだろうか」というコーナーを曲がった上で、「この作品の面白さは、○○にある。その理由としては……」のような結論へと至る。これができて、はじめて価値の伝達が可能となる。
そこで行われるのは、観察であり吟味だ。それが文章をより深いものに導いてくれるのだが、むしろそれは自分自身が対象をより深く理解したことの副産物として捉えられる。言う間でもなく、大切なのは後者の方だ。
また、価値を伝えるためには、適切な言葉を選べる力も必要となる。頭の中に渦巻く思念を、他の誰かに手渡すためには、それに見合う言葉を選ばなければならない。単に、自分が感想をぶちまけて、「ああ、楽しかった」で終わるならば、そうした言葉の吟味などは必要ないだろう。でも、それを「誰か」に伝えるためには適切な言葉が必要だ。結果、そうしたことを繰り返していけば、どんどん自分の言葉は鍛えられていくだろう。
ようするに、十分に価値と言葉を吟味すれば、誰かの非難に負けない勇気が持てる──というのは、あまりに単純過ぎる見立てだろう。ここには、もう少し繊細な要素が関わっている。
対象を吟味すればするほど、私の中に「この良さを伝えたい気持ち」が高まってくる。それを適切に表現する言葉を組み立てていけばいくほど、「このことを知って欲しい」という欲求も高まる。それが、あるラインを超えると、批判される怖さをも上回ってしまい、人は「公開」ボタンを押すことになる。
つまり「書くための勇気」とは、非難を意に介さない剛胆さではない。それは、書き手としての成長をすべて投げ捨てる傲慢さの裏返しであろう。むしろ、非難される怖さをうちに含みながらも、「それでも」と価値を伝えたい気持ちを抑えきれずに押されてしまう「公開」ボタン。そこにある微妙な気持ちこそが「書くための勇気」ではないだろうか。
別にそんなに心配する必要はない。私が「誰か」に向けて文章を書こうとすればするほど、有象無象のやかましい声は少しずつ鎮まっていく。そんな人たちは外野であって、私がやっている「ゲーム」には関係がない。あの「誰か」にこの「価値」が届けば、私の勝ちなのだ。
そのように捉えれば、これは『知的生活の設計』が提唱している、現代的な知的生活だとも捉えられる。この本の「情報発信は贈り物である」という見出しには、以下の文章が続く。
最初のひらめきは、どんな情報がバズるのか、あらかじめ知ることは困難だという点です。
あらかじめわかっているならば誰もがそれについて発信するわけですから、書き手はその記事に人気が出るのかどうかの確信もないまま、先に情報をウェブ上に置くことが必要なのです。
(強調原文ママ)
そのような行為にもまた、やはり「勇気」が関わってくるだろう。つまり、「贈り物をするには、勇気が必要」なのである。喜ばれるかどうかはわからない。でも、ぜひともこれを受け取って欲しい。受け取って欲しいからこそ、丁寧に中身を選び、ラッピングをする。でも、どれだけ努力したところで絶対性は得られない。最後の最後には、絞り出すような勇気が必要となる。
そのような勇気を持って、批評(情報発信)にあたれば、いったい何が得られるのだろうか。結局それも、絶対性的な答えを出すことはできない。でも、だからこそ、まったく「予想外」の結果がやってくることはいつだってありうる。
それに、どちらにせよ、私はその行為のメリットを十分に受け取ってしまっている。対象のより深い理解というメリットを。それだけでもう十分であろうし、それ以外は本当におまけみたいに考えておけば、期待感に押しつぶされることも減るのではないだろうか。
▼目次データ:
第1章 書く理由/批評の意味
第2章 言葉を考える/批評の準備
第3章 言葉を届ける/批評を書く
第4章 言葉を磨く/批評を練る
第5章 言葉を続ける/批評を貫く

