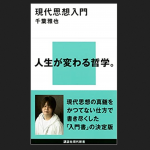単行本として発売されるかもしれないが、とりあえずの雑感を記しておく。
まず文体だが、前作『デッドライン』と比べると描写が緻密で文体全体が濃厚になっている。前作のような軽やかさが少し薄れたようにも思えるが、後述する要素(→言葉の過剰)と関係しているのだろう。
また、二つの作品間で主人公の年齢がぐっと進んでいる。『デッドライン』は修士論文が書けるのか書けないのかで葛藤があったわけだが、本作ではすでに大学に就職しており、日々書き物仕事をしている。有り体に言えば、大人になったわけだ。
しかし二つの作品から感じられる違いは単に年齢や職業(的立場)だけにあるのではない。本作では、ゲイとしての自分の位置づけが主人公の中でかなりはっきりしている雰囲気が感じられる。少なくとも、『デッドライン』の頃のようなどこにいけばいいのかすらもよくわかっていない不安定な感じはなくなり、少しずつ、探り探りに、冒険に出ていけるだけの何かを得ているかのような強度が感じられる。
しかしその強度は、人を超人にしたりはしない。全体的な印象として本作は「恋愛小説」だと感じたが、人の心にある機微や弱さはむしろストレートに描写されていて、しかしそれもまた一筋縄ではいかない。なぜなら、主人公があまりにも言語過剰であるからだ。
本作の一つのしかけとして、主人公がおりおりにツイートする文章が挟み込まれるわけだが、中毒的であると自覚がある私は非常に共感を覚えた。頭の中でいつも「ツイート」を探しているのだ。写真が好きな人が脳内で風景をフレームで切りとっているのと同じで、「短くいい感じに言えること」を脳はほとんど常駐アプリケーションみたいに実行している。
結局それは、Twitterのつぶやきやすさもあるのだが、その背景には言葉という道具に体中を搦め捕られているかのような言語的人間の性質が影響しているのだろう。言葉を「考え」ずにはいられない。単に言葉を発するだけではなく、言葉を通してその事象を考えずにはいられない傾向があるのだ。
ということもまた、それらの人々は考えてしまっている(もちろん、言葉を使って)。言葉・言語・現象・分析といったものが、仕事となり日常の一部と化している人間にとって、Twitterは最高の遊び場であり、言語をなんとか逃がすための装置でもある。頭の中に渦巻く言葉を切り出し、世に向けて放流せずにはいられないのである。一方で、その欲求はまさにそのTwitterによって強められてもいて、人間が主体なのか道具が主体なのかもはや判別がつかない状況である──ということもまた、それらの人々は言葉によって考えるのだ。
言語過剰な人間は、メタ過剰な人間であり、自分が言語過剰であることもまたメタな認識によって理解している。だから、主人公はいつも他人との会話で抑制的に振る舞うのだ。頭の中ではむちゃくちゃ言葉を動かしているのに、人と話すときはむしろ言葉が少なくなる。言葉がありすぎるから、むしろ話せなくなる。考えすぎるから、行動できなくなる。
そのように溜め込まれた言葉=思考は、ある種の熱を帯びてくるのだろう。その熱をうまく逃がせなければ──湯気が出たりはしないだろうが──、頭がどうにかなってしまう。
あるいはいったん熱を溜め込んでしまうのがよいのかもしれない。その熱によってエンジンが止まれば、はじめて違った座席から世界を眺められるようになる。むしろ、そうしなければ言語過剰な人間(=メタ過剰な人間)は、エンジンを動かし続けてしまうのだろう。
ともあれ──本作の読むべき点なのかはわからないが──、Twitter中毒の人間にとっては実にリアリティを感じる作品であった。「ほほう。」以降は共感しすぎてしまって、少し笑ってしまったくらいである。そんな作品はめったにないことは間違いない。